認知科学からのアプローチ。質感を醸成する重要なファクターとしての語彙の問題
中村:日本とフランス、ヨーロッパの気候と景観の違いを取り上げつつ、素材と道具の風土との関わりについて話してきました。では、これらをもうちょっと科学的な視点で考えてみたらどうなるんだろう、我々の視覚の感覚を、例えば認知科学であるとか、生理学であるとか、そういう視点で考えた時に実際どのようなことが、絵の中で、頭の中で起こっているのか。例えば認知科学においてどのようなことが分かってきているのか。
三木:そうですね。認知科学のことを僕が話すのは荷が重いんですけど、今まで分かってることを並べて、後で質感の話と繋げたいと思います。で、これは有名な論文なんですけども、人類学者のブレント・バーリンと言語学者のポール・ケイが、全世界に98種類の言語を調べて、11の基本色彩語があると報告しました。「Basic Color Terms」っていう論文で、最近翻訳が出たんでぜひ読んでいただきたい名著です。当時、カリフォルニア大学バークレー校を中心に行われた調査だったと思います。
言語学とか、人類学っていうのは基本的にはヨーロッパの方で発達したものです。なぜかというと植民地があるからなんですけど。植民地の人たちがどういうような言語を持って、どういうような知覚をしているかっていうことを人類学者や言語学者が調べたわけです。その中でもっとも重要だったのは色だったんですね。色によってどういう語彙があるのか、どういうような認識をしてるのかっていうことが分かるので。昔はですね、色が少なければその色が見えてないとすら思われてたんですが、それは色覚の調査をすることによって色は見えてるけど、語彙だけが少ないんだっていうことが分かったんです。それまでは、人種によって色の感じ方っていうのはかなり違うと思われてたんです。しかしバーリンとケイっていうのは再びダーウィニズムというか、進化論的な発想を呼び起こしてですね、世界各地11語に関してはみんな同じ色を感じてると。2色とか、少ない言語もありますけど、どんどん発達していくうちに分岐していって11まで至るっていうような論文を出しています。ただですね、それはバーリンとケイらによって改定されていて最近は基本色彩語は6色ぐらいじゃないかと言われてたりもしています。
中村:減っちゃったんですか。
三木:「Basic Color Terms」は存在して、白、赤、黄、緑、青、黒の6色は基本色彩語だけどオレンジ、ピンク、紫、茶色、灰色の5色はその組み合わせとして除外されて、11色ではないというように改定されたということですね。
言語の違いや、何か指し示す言語があるかないかで認知も変わる、ということは議論の対象になっています。基本色彩語に関係しているのですが、少なくとも知覚にも影響を与えるんじゃないかということを実証している研究もあります。それはどういう原理かというと、ロシア語には明るい青と暗い青の区別があって、それによって知覚速度がロシア語を母語する人と、そうじゃない人で青いところの反応の速度が違うんです。だから、やっぱり言語によってかなり知覚にも影響を与えるってことが分かり始めてる。ただ「Basic Color Terms」というのは、カテゴリカル・カラーネーミングと言われる広い範囲のことなので、慣用色名のような細かい語彙が、どう影響をするかという研究まだ分かってないと思います。
これは参考ですけどMerz&paulの4583色の色名辞典があるんですが、なんでそんなに英語圏の色の名前が多いかっていうと、元々多かったわけじゃなくて19世紀に人工的なケミカルな顔料とか染料とか、たくさん発明されて急激に増えたんです。
たぶん通常使ってるのは、もっと少ないと思います。で、これは『フランスの色景』の中に書いてあるんですけども分布を見たら結構違うのが面白いなということもありまして。
中村:なるほど。例えばフランス人と日本人でよく見える色が違うということがあると。
三木:言語がそのまま知覚に対応しているというわけではないと思いますが、例えばですね、フランスの色名なんかで言うと明度が低いけども、彩度が高いというのが多いんです。ここの配色とか、あとこういうところは詰まってたりします。
中村:お洒落な色ですね。
三木:つまり日本だったら全部原色にしてしまうところを。
中村:ガンダムカラーになっちゃうところを、落ち着いた、ちょっと洒落てるな、みたいな色になっている。
三木:ちょっと明度を下げればいい。そういうテクニックは日本になくて。だから、日本は元々柳田國男が「天然の禁色」と言ったようにですね、天然の染料ばっかりだったから、彩度の高い色はあんまり出せないんですね、明治以前というのは。
中村:天然染料だとそうですね。蛍光色みたいなのはないですもんね。
三木:ないんです。だから、凄く痩せているし、こうやっぱり身体も痩せてるんですね。
中村:身体が痩せてる?
三木:色を身体に見立てると、ということなんですが、日本の慣用色名は色立体の中でりんごの芯みたいな状態ですね。それとこういうのとフランスなんかでも詰まってるとか。こういうところが多いのはやっぱり。
中村:日本側には全然ないですね。
三木:そうですね。この辺多いのはワインとかね。フランスの色の名前ってどんどん作られてるわけなんですけど、やたら食べ物の名前が多いっていう。だから、食べ物との接点とか、味覚との接点とかも結構やっぱあると思うんです。だから、言葉が知覚に影響を与えるっていうのはあるんじゃないかっていうふうには思っています。
中村:また関西と東京の話すると、大阪から浪人して東京に来たとき、ラーメンとかチャーハンを見て、色がない!と思ったんですよ。ねぎが白いから。なんか東京の食べ物って色がないなと思って。ちょっと寂しいなと思うんですよね。なんだか茶色いし…(笑)。
ところで、これは三木さんが作られたソフトなんでしょうか。
三木:僕がディレクターになって作ったソフトです。
中村:3Dでこの分布を見れるんですね。
三木:はい。西洋人は立体志向なので、たぶん昔は頭の中に描いて作ったんだと思うし、マンセルなんかは本を読んでも色立体ってどうなってるか相当シミュレーションしていて、結構正しいんですよね。
日本にはこういう頭の中で立体をイメージするってなかなか難しいんですけど、西洋人の、彼ら考えた人でも、実際の立体なんか見たことないわけですよ。特にトーンなんていうものは色立体だとリング状になってるわけなので、それを立体で、しかも輪になった部分を想像しろっていうのはかなり難しい話で。おそらく当時の人たちはこういうのを見たかったんじゃないかと思いますけど。こういうのを我々はテクノロジー使って見れるので、凄くラッキー。
中村:凄い。なぜかそれを日本人が作っちゃったわけですね。
三木:そうなんです。僕は日本人じゃなかったんですね(笑)。嘘ですけど。こういうふうに分布なんかが、これ日本の色ですけど。フランスの色なんかは、これかな。これですね。こういう感じ。
中村:全然違う。
三木:特にどこが違うかって言ったらここの、これはトーンって言われるものです。フランスの伝統色は、この辺の色ですね。
中村:素敵な色ですね。
三木:素敵な色なんです。こういうような色が使えたら。
中村:ブドウとか、ワインとか、思い出しますね。
三木:やっぱりね、ちょっと派手なんだけど何となくいい感じになるのは明度をやっぱり抑えてるんですよね。そういうのはやっぱり上手いなって。日本では、この辺の色はないですよね。日本は江戸時代に奢侈禁止令があったんで、四十八茶百鼠とかって俗に言われていて、灰色や茶色が多いとされていますJISのものから取るとそれほど多くないんでけどね。その後、明治以降は外来色がこうやって増えるんですけど。
中村:これはJIS規格ですね。
三木:JIS規格の慣用名の和色名の分布をプロットしています。明治以降は外来色名になるので、カタカナが増えるんですけど。それも結構問題というか、ある程度日本語の名前を…。
中村:当てはめてはいかなかった。
三木:当てはめたこともあるんです。例えば新橋色とかね。あるんですけど、百貨店の人が文学者に依頼した色名とか、でもそれはほとんど残ってないんです。だから、今は由来が分からないカタカナの名前を作ったりとかしてるから、やっぱり感覚と結びつきにくいですよね。フランス人が食べ物と名前でマカロンとか言ってるのとはやっぱ違います。というような問題があって、僕は新しい日本の色の名前を作った方がいいんじゃないかとはずっと提案しています。
中村:日本画の顔料は、出典を知らないからでしょうけど、不思議な色名もたくさんありますよね。
岩泉:そうですね。
中村:漢字で書くし。
岩泉:だから、新橋とか、納戸色(のといろ)とか、あ、いや納戸色(なんど)だ。納戸色とか。
中村:新橋って何色?
岩泉:新橋は水色ですね。
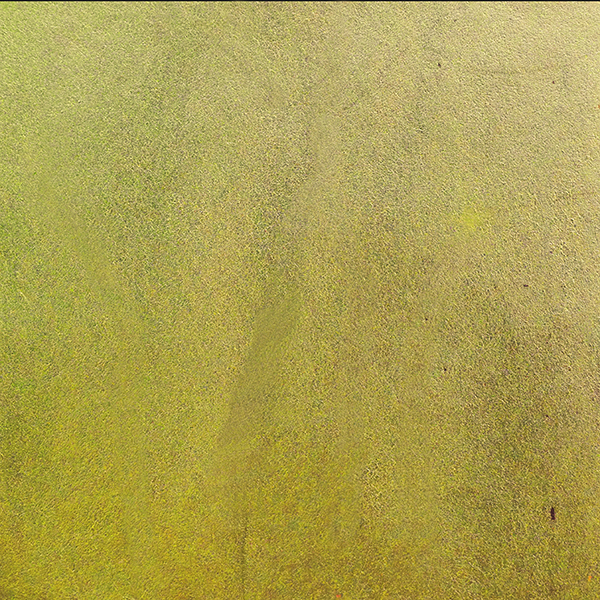
新光箔 《納戸色》

新光箔 《新橋色》
中村:なんで水色なの。
岩泉:それは調べたんですよ。新橋芸者がその頃よく着てた色だから新橋色って言って、納戸色とか、うす納戸色ってそれも調べたんですね。そしたら、暗がりの中で納戸を開けた時の明かり入ってきた暗がりの色が緑がかかったような、青みがかったような色だから。
三木:通じないですよね、今じゃ。
中村:じゃあ、AKB48からいただきましたノリで色名つくってもいいのか。
岩泉:そうですね。新橋色だと初音ミクのミク色になりますかね。
中村:本当だ。初音ミクの色だ。
三木:だから、まさにそういうことでもっとね、だから僕らの世代が知ってる名前でミク色とかつけた方がいいと思うんですね。
中村:「ウルトラマリン」とか「ビリジアン」とか言ってる場合じゃない!と。
三木:そうそう。ミク色って言えばいい。
中村:そうかあ、そういう提案もありですね。フランス人は食べ物から色名をつけているのが多いという話がありましたが。
三木:というのもあるし、味覚も多いっていうのもあるし、フランスの場合だとそのインターナショナル・クライン・ブルーみたいなアーティストがつけるケースもありますよね、ああいうのは結構面白いと思いますね。だから、中村ケンゴ色とか。
中村:自分でも作ってもいいっていうことですよね。
三木:アニッシュ・カプーアがね…。
中村:真っ黒のやつですね。
岩泉:「ベンタブラック」ね、独占しちゃいましたけどね。
三木:独占したね、またそれに対抗してみたいなありますけど。彼らはインターナショナル・クライン・ブルーもちゃんと特許取ったりしてますしね。だから、ちゃんと色に対する権利意識があるんです。この色は僕の色だっていうのがある。
質感に移ったほうがいいですかね。この本にも書いたんですけどミシェル・パストゥローという有名なフランスの色彩学者、元々は紋章学者の方がいて、『ヨーロッパの色彩』っていう本を書いています。
元々、紋章学者で紋章の配色の組み合わせ研究していて、色彩の変化に気づくんですね。どの時点でヨーロッパで色彩革命が起こったかみたいな。大体、12世紀頃に色彩革命が起こったと言われてるんですけど。そこから色彩がどんどん自由になっていくんです。
そういうヨーロッパの色彩の変化を研究してる『青の歴史』っていう有名な本があるんですけど。その『青の歴史」に続いて、緑とか、新しい色を足していってます。『ヨーロッパの色彩』には、色彩っていうとパラメーターが明度とか、彩度とか、色相とかになりますが、日本人なんかは別のパラメーターを持っているということで質感についてふれています。つや消しと光沢ですね。特に写真における印画紙のなんかにつや消しとか、光沢とかって。あれで、日本人の感覚というのを向こうでも知ったと。
中村:つまり、つや消しと光沢っていう区別はヨーロッパにはなかったと。ヨーロッパの人たちは日本人がしている区別を見て気づいた。
三木:日本の印画紙を見て、質感の違いに気づいたってことなんですね。
中村:たしかに日本人はつや消しと光沢、どんな人でも普通にその違いを感じることができそうですね。
三木:そうですよね。普段でもそんなこと感じていますから。じゃあ、その質感に引き続きますね。
<目次>
イベント概要
登壇者の紹介/中村ケンゴによる問題提起
「フランスの色景」と絵画の色彩分析
西洋と比較における日本人の色彩と質感の感覚
なぜ日本の芸術大学では色彩学をきちんと教えないか
風土による視覚の感覚の違い。地域と移動の問題
画材の特性の観点から見る色彩の地理学
認知科学からのアプローチ。質感を醸成する重要なファクターとしての語彙の問題
質感に関する研究について
産業界との関連(自動車や化粧品業界などにおける色彩の研究&ファッション)
まとめ
※トークイベントの記録を随時アップしていきます。
初出「色彩と質感の地理学-日本と画材をめぐって」『芸術色彩研究会』2017年。
<芸術色彩研究会(芸色研)>
芸術色彩研究会(芸色研)は、芸術表現における色彩の研究を、狭義の色彩学に留まらず、言語学や人類学、科学、工学、認知科学など様々なアプローチから行います。そして、色彩から芸術表現の奥にある感覚や認知、感性を読み解き、実践的な創作や批評に活かすことを目指します。
ここで指す色彩は、顔料や染料、あるいはコンピュータなどの色材や画材だけではなく、脳における色彩情報処理、また素材を把握し、質感をもたらす要素としての色彩、あるいは気候や照明環境など、認知と感性に大きな影響を及ぼす色彩環境を含むものです。それは芸術史を、環境と感覚の相互作用の観点から読み直すことにもなるでしょう。
http://geishikiken.info/
