
台湾アーティスト、張騰遠(チャン・テンユァン/CHANG Teng-Yuan) ギャラリーノマル前で
■展覧会概要
Exchange Program:Osaka ↔ Taipei 張騰遠 CHANG Teng-Yuan:HEX展
会期:2015年7月1日(水)-7月31日(金)
会場:Gallery Nomart https://www.nomart.co.jp/
協力: Galerie Grand Siècle (新苑藝術)
後援: 台北駐大阪経済文化弁事処
未来からの眼差し、「地球考古学」の創出
もし現代文明が、遠い未来に発掘される「遺跡」となったなら、未来の知的生命体は私たちの世界をどう解釈するだろうか。そんな壮大な思考実験を、ポップかつ批評的な視点で展開するのが、1983年生まれの台湾の若手アーティスト、張騰遠(チャン・テンユァン/CHANG Teng-Yuan)である。
国立台湾美術館での個展など、母国で確固たる評価を築き、近年は国際的にも活動の幅を広げる張。彼が提唱する「地球考古学(archaeology of the Earth)」は、ポンペイ遺跡のドキュメンタリーから着想を得た独自の概念だ。それは、地球滅亡から数千年後、遠い惑星から飛来したエイリアン「パロットマン(オウム人間)」が、滅びた文明=現代を調査研究するという物語を基盤とする。人間を模倣するがその行動や感情の意味を理解できないオウム(パロットマン)の視点を通すことで、私たちが自明とする価値観やシンボルは一度全てリセットされる。
本作は、台北と大阪のアートシーンを繋ぐ「Exchange Program」の一環として、大阪のギャラリーノマルで開催された。先鋭的な現代美術を発信し続ける同ギャラリーの企画趣旨とも合致した、刺激的な展覧会であった。

展示風景 画像提供=ギャラリーノマル
複眼(HEX)が捉える現代社会の網目
展覧会タイトル「HEX」は六角形(Hexagon)を意味する。無数に繋がり、無限に拡張するハニカム構造は、情報ネットワークが隅々まで張り巡らされた現代社会のメタファーだ。そしてそれは、個々が世界を覗く窓であり、欲望を送受信する昆虫の「複眼」とも重なる。CHANGは、この複眼的な視点を通して、グローバル化の奔流の中で私たちが立つ位置を問い直す。本展は、そのコンセプトを体現する大きく3つのセクションで構成されていた。
第一に、展覧会名と同名の作品《HEX》。これは、CHANGが事前に日本人へ「感情の単位」について尋ねたアンケート結果を反映させた、巨大な脳内マップともいえるペインティングである。 第二に、パロットマンたちの奇妙な調査活動を描いた一連のペインティング群。 そして第三に、インターネットを主題とした大作《The God of Web(網路之神)》三部作だ。これらが相互に作用し、「地球考古学」の世界を多層的に構築していた。
意味を剥奪された日常:感情と死の再解釈
《HEX》において、パロットマンは日本人の感情を研究する。例えば「楽しさ」の単位は「トランポリン」と設定され、「おでかけ前日の楽しさ=30×トランポリン」として、パロットマンがひたすら跳ねる姿で描かれる。また、「悲しさ」の単位はアニメ『フランダースの犬』の最終回であり、「財布を落とした悲しさ=5×フランダースの犬」として、ネロとパトラッシュが昇天する場面をパロットマンたちが無表情に観察する。私たちにとっては既知の感動や悲哀が、彼らのフィルターを通すと、意味不明な儀式にしか見えない。このズレは、我々の文化的な「当たり前」がいかにローカルで、脆い基盤の上にあるかを突きつける。

《HEX》

部分拡大 《HEX》フランダースの犬の最終回場面
同様の視点は、《午睡和生命逝去的差別(昼寝と生命が失われることの違い)》でより先鋭化する。横たわる巨大な鳥の隣で、同じように寝転ぶパロットマン。彼らは「死」と「眠り」の違いを理解するため、その状態を模倣している。シェイクスピアが「死ぬは眠ること」と綴ったように、両者は古来より重ねて語られてきた。だが、生命維持のための休息と、不可逆的な生命の停止は、我々にとっては決定的に違う。しかし、その違いを私たちは本当に理解しているのか。コミカルに見えるパロットマンの姿は、鑑賞者の内面にある死生観を静かに揺さぶり始める。
》部分-scaled.jpg)
部分拡大 《The Difference Between a Nap and Loss Life(午睡和生命逝去的差別)》(昼寝と生命が失われることの違い)

《The Difference Between a Nap and Loss Life(午睡和生命逝去的差別)》(昼寝と生命が失われることの違い)
新たな自然か、逃れ得ぬ罠か:インターネットへの問い
展覧会の白眉は、インターネットをテーマとしたペインティング三部作《The God of Web(網路之神)Ⅰ~Ⅲ》であろう。ここでは巨大なWi-Fiルーターが、それぞれ太陽・空気・水といった、生命に不可欠な自然の恵みとして描かれる。Wi-Fiの電波を浴びて植物が育つ光景は、現代人が情報通信インフラなしには生存できない現状を的確に、そして皮肉を込めて描き出す。

展示風景 ペインティング三部作《The God of Web(網路之神)Ⅰ~Ⅲ》
《The God of WebⅡ》では、太陽に見立てられたルーターに吸い寄せられるようにパロットマンたちが列をなす。その光景は「ハーメルンの笛吹き男」を彷彿とさせ、利便性の追求が我々をどこへ導くのか、という不穏な問いを投げかける。
》-scaled.jpg)
《The God of Web Ⅱ(網路之神 Ⅱ)》
《The God of Web Ⅲ》に描かれる無数のマス目は、規格化された情報や都市の建築物を思わせる。空き家が増加する一方で、なおも箱モノが建設され続ける日本の現状とも重なり、鑑賞者は思わず自国の社会構造にまで思考を巡らせるだろう。絵画に込められた多様なモチーフは、読み解くほどに鑑賞者を引き込み、批評的な考察を促す力に満ちている。
》-scaled.jpg)
《The God of Web Ⅲ(網路之神 Ⅲ)》
俯瞰することで見えてくる“今”という遺跡
張騰遠が創出した「地球考古学」というフレームは、鑑賞者を日常から切り離し、現代文明の「傍観者」へと変える巧みな装置である。未来のエイリアンという異質な視点を借りることで、私たちは自らが属する社会や文化を、まるで歴史上の遺跡を眺めるかのように客観視し始める。当たり前だと思っていた価値観、疑うことすらなかった日常の営み。それらが一度相対化されたとき、初めてその奇妙さや歪さが露わになるのだ。
同じ枠組みの中にいては、その構造を認識することはできない。現代アートが持つ重要な役割の一つが、こうした認識の変革、すなわち世界の見方を変えてしまうほどの「破壊と創造」にあるとすれば、本展はその醍醐味を存分に味あわせてくれるものだった。コミカルなキャラクターと緻密なコンセプトを両立させながら、現代社会が内包する普遍的な問いを浮かび上がらせた張騰遠。彼の複眼的な視点は、私たちが生きる「今」そのものが、未来にとって最大の謎であり、最も興味深い研究対象であることを教えてくれる。
■初出 パンのパン04 近現代美術とコンテンツとインターネット特集号(上) 68-73頁 | 発行元 きりとりめでる | 2019.11発行
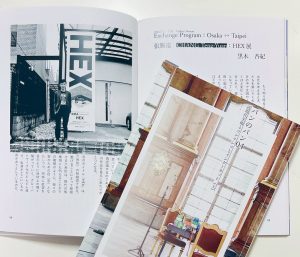
パンのパン04 近現代美術とコンテンツとインターネット特集号(上) 68-73頁
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■展覧会紹介ページ Gallery Nomart | Exhibition
■張騰遠HP CHANG Tengyuan HP – CHANGTENGYUAN HP
