「モダン・アート」、「コンテンポラリー・アート」、「アート・アンド・デザイン」、「インターネット・アート」等々。ふだん私たちは、実に幅広い意味において、この「アート」という語に出会う。今日、私たちが「アート」という語に触れるとき、その意味合いを決定づけている要素は、いったい何だろうか?
EUGENE Studioは、この「アート」という語の意味とその領域を強く意識すると同時に「アート」そのものの領域とは本来異なる実社会において「アート」の領域から発する様々なプロジェクトを実践するアーティストだ。
「アート」という語の捉え方を20世紀以降のアートの大きなフレームの中で紐解きながら、彼らの《White Painting》について触れたい。
***
まず美術史や芸術学の用語である「ファイン・アート(純粋美術)」という概念を簡単に紐解くことから始めよう。「ファイン・アート」とは、一般には、デザイン、建築、工芸等のように私たちの実生活や実社会において機能や用途を併せもつ「アプライド・アート(応用美術)」の対義語であり、作品自体が機能や用途を併せもたない純粋な表現による「アート」を指す。つまり、その表現物であるオブジェが私たちの実生活や実社会では何も役に立たないもの、消費されることがないもののことだ。さらにいうと、美術館やギャラリーに、収集され、展示され、そこを訪れる人びとに鑑賞されることで初めて成立する「アート」だともいえる。(衣服や器のようなデザインは、美術館やギャラリーの中に収集され、展示されることがあるが、本来人びとの生活の中で使用される機能を併せもっている。それに対し「ファイン・アート」は生活の中で使用され、消費されることはない。「ファイン・アート」を消費することは、鑑賞することである。衣服のように、着用されることで擦れたり汚れたりすることはない、あるいはそうあってはいけない。) 実は、冒頭に挙げた幾つかの「アート」という語は、ほぼすべてこの「ファイン・アート」を指している。それはまた、西欧近代以降の「アート」、あるいはその幹から派生した「アート」のことである。今日私たちが美術館やギャラリーという場所で眼にする「アート」作品の多くは、ほぼこうした「ファイン・アート」の範疇にあるもの、あるいはその性格を志向するものなのである。
「ファイン・アート」の特徴的な概念が生まれたのは、20世紀初めの「モダン・アート」初期の歴史形成期に遡られる。西欧においては、人びとの実生活や実社会の中で機能や用途を併せもった「アート」から「ファイン・アート」が抽出されることで、その歴史や価値の規範が生まれてきたことをあらためて思い起したい。「モダン・アート」初期の歴史物語において「ファイン・アート」の起源は、礼拝堂という建物空間から独立し、次第に自律していった画像(聖像)の発展的な流れにその端緒を見出すことができる 。*1 かつて人びとの共同的な精神生活を満たした説話のための装置である建物の一部(壁画、祭壇画)から切り離され、任意に移動可能となった板絵、カンヴァスへと時代を下りながら発展していった画像が、今日の「ファイン・アート」としての「絵画」なのである。(「絵画」はこうして移動可能になるとともに奥ゆきを放棄し平面化していった。) この画像の発展は、建築という総合的な構築物を創造する集団的な制作行為から、個人による個性的なオブジェの制作行為へと向かい、アルチザンから個人のオリジナリティーをもったアーティスト概念の誕生へと結びついていく。そして絵画や彫刻は、近代以降、礼拝堂ではなく美術館やギャラリーという「ファイン・アート」のための特別な空間の中で鑑賞(消費)されるようになった。この特別な空間は、今日では世界中に遍在する美術館やギャラリーの内部空間「ホワイトキューブ」といわれるものであり、「ファイン・アート」という概念を保証する社会的な機構、制度を支える。いいかえれば、「モダン・アート」以降のアート≒「ファイン・アート」とは、西欧の聖像破壊の流れにおいて、元々は人びとの精神的な実生活と直につながったホリスティックな環境から、次第に切り離され純粋なものとして抽出されてきた「アート」のことなのだ。過去において礼拝のための機能をもった聖なる画像は、時代の経過の中で世俗化し、今日では美術館やギャラリーの内部に置かれ、来訪者の鑑賞行為のための個々に独立したオブジェへと移行したのである。今日の美術館やギャラリーの内部では、古美術の聖像も、印象派の風景画も、ポロックのアクション・ペインティングも来場者にとっては等しく鑑賞するための個別のオブジェなのである。
***
このように「アート」は、美術館やギャラリーという特殊な環境の中で自律し個々に鑑賞されるためのオブジェへと変容してきたわけだが、それ以降、私たちが生きる21世紀の今日から見ると、さらにどのような特徴ある変化を経たのか。一言でいえば、1960年代後半から1970年代にかけてのコンセプチュアル・アートがもたらした「アート」の変容がそれに該当すると思われる。では、コンセプチュアル・アート以降の「アート」とそれ以前の「アート」とは何が異なるのだろうか。
コンセプチュアル・アートの作品は、日常的なオブジェ、構造物、写真、映像、様々なドキュメント類(特に今日ではWEBとつながったデバイス等も)の組み合わせから構成され、それらが設置された空間全体における、各々の要素の関連性こそが作品を成立させている 。*2 時には、この空間の中でパフォーマンスが行われ、鑑賞者自身が作品に何らか関与することで、作品の意味やコンテキストが更新されることもある。コンセプチュアル・アートの作品では、鑑賞者は絵画や彫刻のように個々のオブジェを独立した作品と見なして鑑賞するわけではない。したがって、このような作品の成り立ちから、コンセプチュアル・アートの作品は、インスタレーションと呼ばれ、鑑賞者は作品の構成要素である個々のオブジェの素材やフォルムの魅力を絵画や彫刻のように楽しむ(鑑賞する)というより、むしろ空間全体の関連性から伝えられる何らかのメッセージや意味を受け取る。つまり、作品自体が空間の中の設置物(インスタレーション)として一種のコミュニケーション装置となるのである。
なるほど、20世紀初頭に生まれた「ファイン・アート」は、このように1960年代後半から1970年代以降、鑑賞のための個別のオブジェからメッセージや意味を伝えるコミュニケーション装置へと大きく変容したことが20世紀の美術史の流れの中に見て取れるだろう。しかし反対に、こうした変化の中でも一貫して変わらぬ要素とは何だろう。一つには、コンセプチュアル・アート以前の「アート」も、それ以降の「アート」も基本的には美術館やギャラリーの内部に置かれ、来訪者に鑑賞されることで「アート」として成立していることである(しかし、今日では美術館やギャラリーの内部だけでなく、街中やWEB環境といったそれらの外部にも確かに存在するようになったのだが……)。つまり、私たちがよく耳にする「アート」とは、「モダン・アート」であっても「コンテンポラリー・アート」であっても、概して変わらぬ性格は、「アート」がかつてのように人びとの精神的な実生活と直につながったホリスティックな環境とは完全に接続が断たれているということなのである。いいかえれば、創造者にとってはオリジナリティーを追求する個性の表現として、あるいは鑑賞者にとっては、美的な鑑賞(観照)のために賞賛され、切望されるオブジェとして、近代以降の「アート」は純化していった。このことは、創造者である作り手が「アート」の外側にある人びとの生活や社会から距離を置くようになったこととは対照的に、美術館やギャラリーという場を通じ批評家や鑑賞者といった受け手の側が「アート」の意味や解釈等をめぐる話や議論の活性化のほうへといっそう向かっていったことに関連するのだ。とりわけ、コンセプチュアル・アート以降の「アート」は、作品自体の外側の様々な情報要素とつながり易く、コミュニケーション的・媒介的性格を帯びてメッセージや意味の生産をいっそう促すものとなったのである。
近代以降の「ファイン・アート」の傾向を要約すると、おそらくこのようになるだろう。
***
「ファイン・アート」という用語を頼りに、「アート」という語のシンプルな紐解きを試みたが、こうした「アート」をめぐる大きな流れを踏まえるとEUGENE Studioの《White Painting》はどのような意味をもつのだろうか。
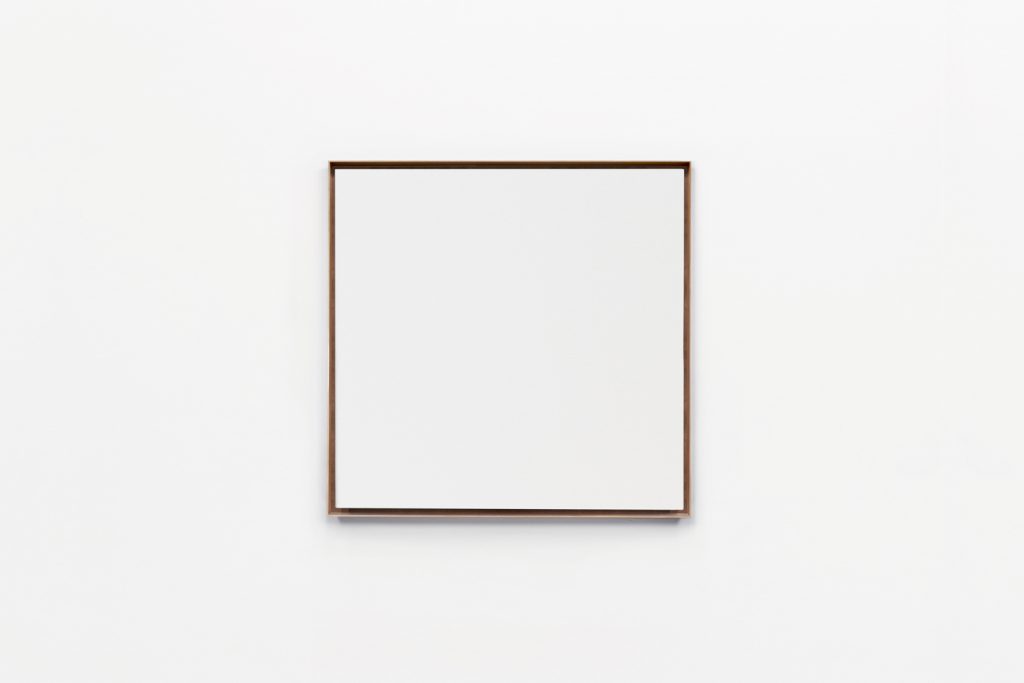
EUGENE STUDIO, Juliette, Sandra, Mitch, Wills, Gillies, Ergas, Asheron, James, Lilly, Thomas. P, Elias, Sofia, Victoria, Mackay, Jamin, Amelius, Prince, Cathy, Valerie, Keiny, Peter, Dona, Sam, Zaret, Christina, Laurencie, Owel, James, Kairy , Frances, Thom, Sugay, Marien, Kinbary, Kalen, Morry, Callen, Mut, Elen, Bruno, Peter, Daele, Clara, Benjamin, Charlotte, Michael, Ryan, Ina, Diego, Javia, Candelas, Robin, Rucaro, Daniel, Rumi, Benney, Sarah, Emily, Jack, Peter, Kevin, Safiya, Trisha, Eric, Danielle, Paul, Floyd, Alexis, Carlos, Nydia, Samantha, Daniela, Michael, Dom, Matt, Todd, Ava, Cailin, Melissa, Kirby, Alexandra, William, McGuiness, Liliana, Francisco, Daniel, Patricia, Anna, Dalia, Ricardo, Diana, Maribel, Barbara, Gabriela, Cristel, Kenia, Lorenzo, Gladys, Alberto, Carlos, 2017, Canvas, 1700x1700mm.
Courtesy of the artist
©EUGENE STUDIO / Eugene Kangawa
《White Painting》は、表面に何も描かれていないカンヴァス作品であるが、このカンヴァスには、100人程の人びとによる接吻が実際に刻印されている。この作品は、シリーズ化されており、このカンヴァスへの接吻は、継続的にアメリカ、メキシコ、台湾で街往く人びとに声を掛け協力を得て制作された。現在、600人以上の人びとの参加によって、幾つもの作品が完成している。また、このカンヴァスへの接吻という行為は、参加者が各々の愛、もしくは愛するひとを思い浮かべて自由に語るシーンがドキュメントとして撮影され、撮影時に実際に使用されたiPhoneによって再生される。カンヴァス自体では表現されえないプロセスとして存在したリアルな舞台がカンヴァスの傍らにドキュメントとしてセットされた作品なのだ。*3 この接吻という行為への参加は、制作者の予想を超え、協力を呼びかけた人びとに抵抗なく受け入れられたという。ここには、ソーシャル・メディアが人々の日常生活に浸透した今日のグローバル社会において、「愛とは何か」という人間にとって身近で普遍的なテーマに誰もが共感し、その場のある状況に瞬時に溶け込むあり様をリアルに反映している。

EUGENE STUDIO, Series of White Painting, Still from video.
Courtesy of the artist
©EUGENE STUDIO / Eugene Kangawa
《White Painting》は、その形式を見る限り20世紀初頭のシュプレマティズムの画家、カジミール・マレーヴィチの《黒の正方形》(1915年)―マレーヴィチは同じく《赤の正方形》や《白の正方形》も制作している―を彷彿させる。マレーヴィチの無対象絵画は、かつての精神的な実生活と直につながったホリスティックな環境とは完全に接続を断った近代の「ファイン・アート」の性格をよく表す。マレーヴィッチは美術史やそれが蓄積された美術館の破壊を主張したというが、それは、「アート」の外側にあるものとの接続を断ち、個々の純粋な「アート」オブジェを革新的にゼロから創造しようとしたからなのだろう。EUGENE Studioの《White Painting》はどうだろうか?この作品も一見すると、マレーヴィチの《黒の正方形》(1915年)と同じ無対象のカンヴァス作品であるが、カンヴァスという物質的なメディウムにすべてこの作品を構成する要素があるわけではない。すでに述べたように、《White Painting》は、シリーズ化された継続的な作品であり、第三者の協力によるパフォーマティヴな要素がドキュメント映像というかたちでセットされている。いいかえれば、マレーヴィチの《黒の正方形》は、カンヴァスという物質的なメディウム自体にモダニズムの美学的に解釈可能な要素が集約しているのだが、《White Painting》はといえば、カンヴァスという物質的なメディウムがメディウム以外の外側の要素をともない、現実世界の日常性へとこの作品をつないでいく鍵となっている。

EUGENE STUDIO, Series of White Painting “Trinity”, 2017, Canvas.
Courtesy of the artist
©EUGENE STUDIO / Eugene Kangawa
***
今日の「アート」が置かれた状況において、《White Painting》はどのような意味をもつのだろうか。私たちが「アート」と出会う場は、先に見てきたように、物質的なオブジェそのものと出会える美術館やギャラリーを中心としながらも、もはや「アート」に関する適切な情報を見出す場はインターネットが中心だ。美術館やギャラリーのWEBサイトばかりか、ソーシャル・メディアによってもそうした情報を検索するようになった。私たちは美術館やギャラリーを実際に訪れる頻度よりも、インターネットで「アート」に接することの方がはるかに多い。今日の「アート」が置かれた状況で最も特徴的なことは、「アート」は物質的なオブジェの状態から電子的な情報となってWEBのネットワークの中へと組み込まれるようになったことだろう。作品のユニークさやオリジナリティーという従来の「アート」の価値(アウラ)が物質的なモノとしての近づき難さや希少性に基づくものであるのに対し、今日のこうした情報化した「アート」の画像やそれらに付随する要素は、ネットワークの中に露出されることで受け手の興味を喚起する。「アート」は、情報のネットワークに付属し、あたかもグローバル経済の中で循環するマネーのように循環するものとなった。そのネットワークの中には、作品の付随要素として、制作者も、その他の関与者に関する情報も、あるいはそれらについて伝えるメディア等の様々な関係要素がもつれ合いながら、その作品の複雑な意味を形成している 。今日のWEB環境のもとでは、作品とともにそれにひもづく様々な関係要素が情報として受け手の前に立ち現れる。
《White Painting》がマレーヴィチの《黒の正方形》(1915年)と決定的に異なるのは、物質的なモノとしての絵画(カンヴァス)を介すことでひとつの行為を共有したごく小規模の人びとの集まりが街の中に現れ、再び何事も無かったかのように消滅した現場(シーン)が、絵画自体の他に確かに存在しているという事実であろう。この現場は、絵画という物質が介在することで生じ、物質であるがゆえに移動することで他の国、都市、街でも同様に生じうるのである。そこには、かつて人々が精神的な実生活の中で聖者を敬愛し聖像に接吻したように、今日の人びとによる、愛、もしくは愛するひとを思い浮かべるという日常的な行為への共感と、他者による接吻に自らの接吻を重ね合わせるという寛容な態度によって、第三者の間の参加性が支えられていることが見て取れる。《White Painting》は、「絵画」の伝統的な流れに接続されたカンヴァスという物質的なメディウムでありながら、それ自体の外側に舞台装置のようなものを形成し、そこに集う匿名の参加者がメディウム自体をも更新する作品なのである。これはまた、継続的なプロジェクトであり、「絵画」として美術館やギャラリーに展示されることもあれば、WEBを通じて情報として循環し、無数の受け手の前に露出していくものともなる。
《White Painting》は、「ファイン・アート」における「絵画」形式(フォルム)を保持した作品として受け手に鑑賞される個別のオブジェであると同時に、人びとの日常世界に束の間の小さなコミュニティが出現するための媒介となり、さらにはWEBの中に循環して無数の受け手の前に現れていくのである。こうした「絵画」自体の外側(現実世界の日常性)のほうへと直接のつながりをもつ性格がこの作品の今日性なのだろう。
***

EUGENE STUDIO, Beyond good and evil, make way toward the wasteland., 2017, Ceramic, iron, wood, glass, ash, other, 9000×3200×4200mm.
Courtesy of the artist
©EUGENE STUDIO / Eugene Kangawa
EUGENE Studioは、《White Painting》のような「アート」とともに、未来の農業による生活を描いた《Agricultural Revolution 3.0》のようなリサーチやカンファレンスを実際に行うことで次の社会の創造を目指す活動を実践している。彼らにとってこれらの活動の間には境界が存在しない。それは、実社会との接続を断たれた「ファイン・アート」を今日の状況に即したやり方で再び実社会へと接続し直していく活動ともいえよう。EUGENE Studioの活動は、《White Painting》の第三者によるパフォーマティヴな参加性のように、現実世界への直接のつながりとして「アート」の領域を押し広げ、様々な協働の枠組みを創っていく継続的なプロセスなのである。
- Julius Meier=Graefe, Modern Art; being a contribution to a new system of aesthetics, London, W. Heinemann; New York, G.P. Putnam’s Sons, 1908, P. 111.
- Boris Groys, Introduction-Global Conceptualism Revisited, e-flux journal #29november 2011, http://worker01.e-flux.com/pdf/article_265.pdf
- David Joselit, Painting Beside Itself, October Fall 2009, No. 130, pp. 125-134, https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/octo.2009.130.1.125
