
Yoshiaki Inoue Gallery
展覧会名:井上廣子/Hiroko Inoue “Being in the Face+交差するまなざし”
会期:2025年10月17日〜11月8日
会場:Yoshiaki Inoue Gallery
現代社会が直面する最も重く、避けがたい現実の一つ、すなわち「難民」というテーマに、真正面から芸術的探求を試みた井上廣子(Hiroko Inoue)の個展「井上廣子/Hiroko Inoue “Being in the Face+交差するまなざし”」が、2025年10月17日から11月8日までの期間、大阪・心斎橋のYoshiaki Inoue Galleryにて開催された。本展は、作家が長年向き合ってきた「不在」のテーマから、社会の周縁に追いやられた人々の「存在」の核心へと踏み込んだ最新シリーズ《Being in the Face》を軸に構成され、私たちが生きる世界の分断と、その根底にある人類の根源的な問いを突きつける、極めて重要な批評的提示であった。
Yoshiaki Inoue Galleryの多層的な空間に展開されたのは、紛争や迫害から逃れ、ドイツにたどり着いた難民女性たちの深く、しかし揺るぎない眼差しである。彼女たちの顔は、単なる記録写真として存在するのではなく、特殊な技法によって物理的な「傷」と「封印された沈黙」を纏い、私たち鑑賞者に、倫理的な対峙を迫ってくる。この展覧会は、一人の芸術家が、世界の痛みに対してどれだけ深く共感し、その根源的な問いに迫ることができるのかを示す、現代アートにおける応答である。

会場風景
井上廣子の芸術の系譜:「不在」から「存在」の主張へ
井上廣子の芸術活動の根幹には、一貫して社会の片隅に追いやられた人々の「魂の軌跡」を探求する姿勢がある。彼女の活動は1992年に現代美術家として本格化するが、その作風を決定的に転換させたのは、1995年の阪神淡路大震災の経験である。この出来事は文明社会の脆弱さを露呈し、彼女は社会の弱者、隔離され孤独にさいなまれる人間の心に寄り添う作品へと主題を転換させた。
彼女のキャリアを特徴づけるのは、その国際的な活動スタイルだ。1998年に「大阪トリエンナーレ」でデュッセルドルフ市・関西ドイツ文化センター特別賞を受賞したことを契機に、翌年からドイツにアトリエを持ち、現在まで日本とドイツを往来しながら制作を続けている。
初期の代表作である写真シリーズ《不在 Absence》(1997-2001)は、精神科病院や隔離施設の窓や人のいない病室を撮影したモノクロ写真を布に現像したもので、文字通り「目に見えないものの存在、すなわち『不在』というテーマ」を一貫して追求するものであった。その後も、世界各地の高校生が目を閉じて立つ写真インスタレーション《Inside-Out》(2005-2013)では、地域紛争やDVの犠牲となる女性や子どもたちへの関心から、初めて人物を被写体とした。また、2011年の東日本大震災後の《Mori:森》(2011-2012)や、有害物質を含む冷却水に着目した《MIZU》シリーズ(2016-2024)など、彼女の作品は常に、人間の存在、生命の根源、そして社会が抱える病理と深く結びついている。
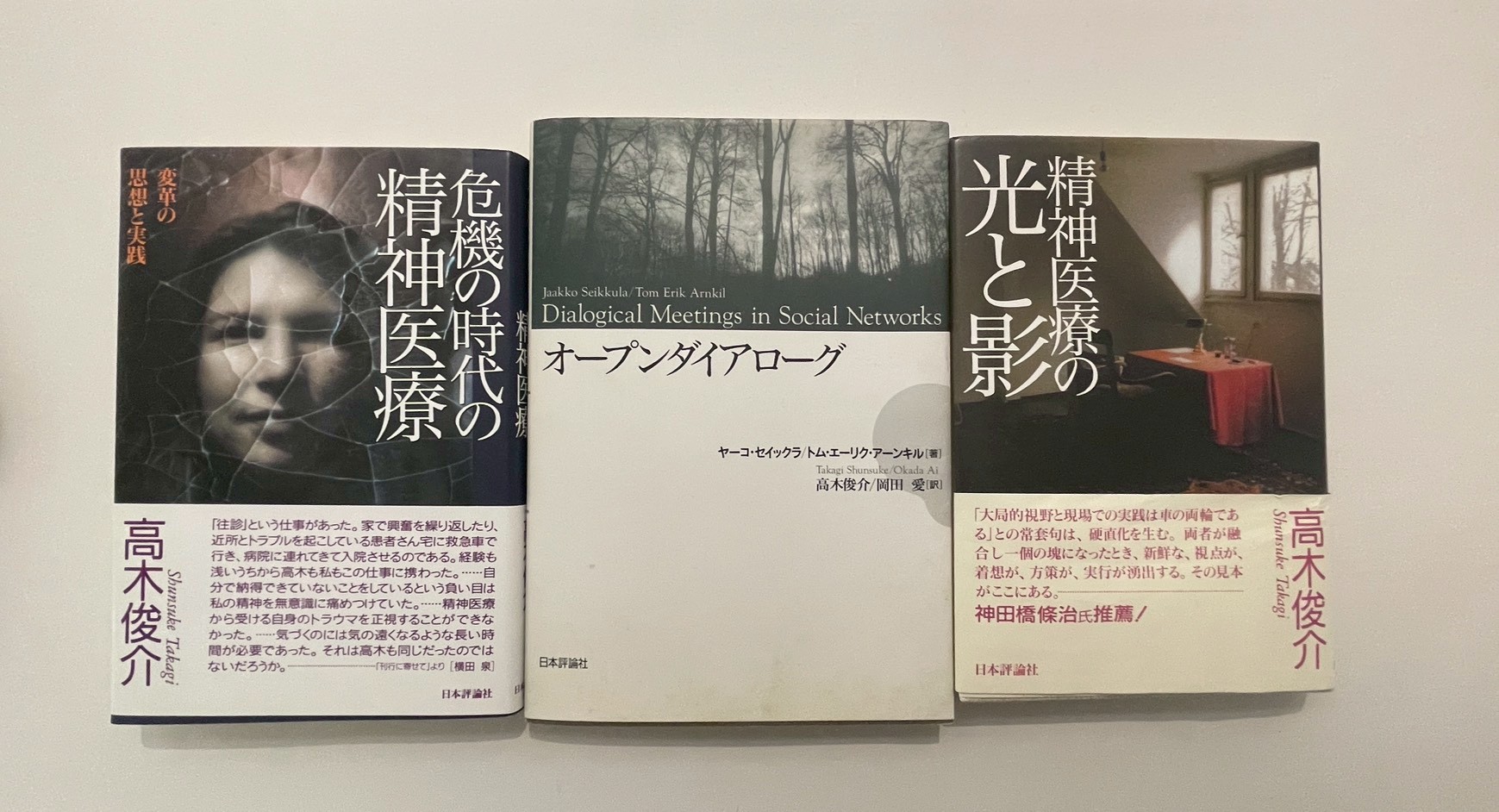
書籍の表紙を飾った井上廣子の作品
そして2022年頃から、井上はベルリンの難民キャンプに通い始め、難民女性たちとの対話を重ねる中で、彼女たちの肖像を作品化する《Being in the Face》シリーズへと至る。これは、長らく「不在」を探ってきた作家が、遂に「存在」の絶対的な主張を前面に押し出した、芸術家としての新たな到達点と位置づけることができる。

ドイツ・ベルリンにある 難民キャンプ (『宙づりの小屋』の窓部分に使われているカラー写真と同じもの)
《Being in the Face》:剥き出しの「生」と痛みの痕跡
本展の主軸をなす《Being in the Face》シリーズの作品群は、井上が難民女性たちと信頼関係を築いた上で撮影を許されたポートレートである。ウクライナ、シリア、アフガニスタン、アフリカ諸国など、様々な出自を持つ女性たちが、画面の中央で私たちを直視している。彼女たちの眼差しは、時に穏やかでありながら、決して逃げない、揺るぎない「生の主張」を宿している。この強い視線は、私たちに「あなたは誰なのか、あなたを見るわたしは誰なのか?」という、人間関係の根源的な問いを突きつける。
井上は、このポートレート作品の表面に、透明なワックスの層を重ねるという、独自の技法を用いている。このワックス層は、写真に写された彼女たちの「封印された沈黙を保護し、保存」する役割を果たす一方で、その表面には、冷えて固まる際に生じた無数の「細かいヘアラインクラック(ひび割れ)」が網の目のように広がっている。この写真作品のクラックこそが、井上廣子が表現の核心として意図したものだ。作家は、このひび割れを「彼女たちのこれまでの人生の心や体の傷や痛み」のメタファーとして表現する。

《Being in the Face #24_Aminwaa(Ghana)》 2025
また、私たち鑑賞者にも、「ひび割れた作品を制作することによって、過去の悲嘆から未来への歩みを表現出来ないだろうか」と問いかける。ひび割れは、破壊の痕跡であると同時に、内包されたエネルギーが外へと解放されようとする、未来への希望の萌芽にも見え、情感豊かな解釈を促す。この技法は、単なる写真の記録性を超えて、彼女たちの受けた心の深い傷が、今もなお存在し続けていること、そしてその傷を抱えながらも生きることを選んだ「穏やかな硬さ」を象徴している。
群像のまなざしと、宙づりの「小屋」が示す難民の宙ぶらりんな状況
Yoshiaki Inoue Galleryの2F展示空間は、難民女性のポートレート写真とインスタレーション《小屋》によって、緊迫感と情感に満ちた対話の場を創出していた。2Fの壁面に展示されたポートレートは、小さめのサイズで、4つまたは5つの写真が塊となって配置されており、あたかも難民という集団、あるいは家族の群像を見ているかのような印象を私たちに与える。シリア、アフガニスタン、ウクライナなど、異なる国や背景を持つ女性たちが、画面の中央で鑑賞者をまっすぐに見つめている。この「生の顔」は、私たちに「あなたは誰なのか?」という哲学的な問いを投げかけると同時に、美術批評家の小勝禮子が言うように、弱い立場に置かれながらも「生きること、ここに存在することをしっかりと主張している」と強い意志を伝えている。

2F 展示風景

2F 展示

2F 展示
この写真作品の表面の「透明なワックスの層」に見られる無数の「細かいヘアラインクラック」。この視覚的な「ひび割れ」こそ、作家が作品に込めた最も深い情感であり、それは、戦争や迫害から逃れてきた彼女たちが負った「心の深い傷」の物理的な表現であることに、鑑賞者は気づかされる。このクラックは、単なる表面的な装飾ではなく、彼女たちの痛みが、今この瞬間も存在し続けていること、そしてその痛みと共に生きる「穏やかな硬さ」を象徴しているのだ。

《Being in the Face #1’_Farida》 2025
そして、2F中央に配されたインスタレーション『宙づりの小屋』は、この個人の痛みを、難民問題という構造的な現実に結びつける、批評的な装置として機能する。井上廣子自身が明かすように、この小屋は、ポートレートの女性たちへの取材に基づき、「強制送還を恐れ、ましな住居と仕事を待ち望む」彼女たちの、「住居や仕事がまだ決まっていない、宙ぶらりんの状況」を表現するために、地面に着けずに吊り下げられている。

『宙づりの小屋』 ギャラリー奥より望む

『宙づりの小屋』のポートレート ただ一人、素性を明かしてくれた「ユリア」とインタビューシート 《Being in the Face #9_Julia(Ukraina)》 2025
『宙づりの小屋』は、法的な地位、経済的な基盤、そして心理的な安心感のすべてが不安定な、難民たちの存在のメタファーである。小屋の窓部分には、現実の難民キャンプを撮影したカラー写真が使われており、ギャラリーという安全な空間と、遠い場所で続く過酷な現実との間に、強烈な「交差するまなざし」を生み出している。

『宙づりの小屋』 ギャラリー入口より望む
増幅された“顔”が語る──難民女性ユリアの物語
3Fの展示会場へと足を踏み入れると、その空間構成の意図がより明確になる。3Fには、2Fと同様に《Being in the Face》シリーズの難民女性のポートレート写真が展示されているが、そのサイズはより大きく、一対一で鑑賞者に対峙するような迫力をもって配置されている。

3F 展示風景
群像的な展示空間から巨大な個の肖像空間へと移行することで、作家は難民問題の集団的な側面から、個の尊厳と個の痛みへと、私たち鑑賞者の意識をより深く引き込もうとしている。大判のポートレートに対面するとき、写真の表面に広がるワックスのクラック—彼女たちの心の深い傷—は、より詳細に、より生々しく私たちの視覚を捉えることになる。

《Being in the Face #18_(Afghanistan)》 2025
この空間では、ポートレート写真を通して、ウクライナのニコポル出身の難民女性、ユリアの個人的な悲劇が、切実なものとして迫ってくる。ユリアはインタビューの中で唯一、自分の素性を打ち明けてくれた難民女性だ。ロシアの全面戦争により、夫を戦場に残し、砲撃の恐怖から子どもたちを連れて国境を徒歩で越えてきた。彼女の故郷は毎日砲撃され、多くの友人や同僚が亡くなったという生々しい証言は、単なる報道を超え、芸術作品として提示されることで、その普遍性と切実さを増幅させる。3Fの展示は、私たちに、難民とは統計上の数字ではなく、私たちと同じように愛と痛みを抱えた「個」であることを、逃れられないスケールで突きつけているのである。

3F 展示 右端がユリア
ドイツの難民・移民史と「ロールバックする歴史」への問い
井上廣子がドイツを主な活動拠点の一つとしていることは、彼女の作品を読み解く上で不可欠な文脈を提供する。ドイツは、歴史的な経緯と戦後の経済復興の必要性から、移民・難民を受け入れてきた経緯があり、特に2015年の難民危機では、寛容な姿勢を示した。
しかし、難民受け入れの増加は、社会の分断や右派ポピュリズムの台頭という現実ももたらしている。井上廣子は、ヨーロッパでの生活の中で、「歴史がロールバックしているのではないかと思う様なドイツの分断化を象徴する光景」に何度も遭遇しているという。彼女は、この状況の根底にある「何か」、すなわち「人間とは、歴史とは、教育とは何なのか」という、文明社会の構造的な病理について深く考察し、作品を通じてそれを問いかけている。
難民女性のポートレートに刻まれた「ひび割れ」は、故郷を追われた個人の深い心の傷であると同時に、寛容と排他性の間で揺れるドイツ社会、さらには世界全体が抱える構造的な「傷」のメタファーでもある。井上廣子は、この大きな問題の根底に、人間が繰り返し歴史から学ばない愚かさ、そして他者への共感の欠如があるのではないかと、その芸術的直感をもって問いかけているのだ。

《Being in the Face #7’_Saadia(Syria)》 2025
情感の織りなす現代アートの新たな領域
井上廣子の作品の価値は、単なる社会批評にとどまらず、写真という冷徹なメディアに、ワックスという温かく、しかし脆い物質性を加えることで、情感を深く織り込んでいる点にある。ワックスの層は、被写体の「沈黙」を封印し、保護する一方で、凝固の際に生じるクラックは、封じ込めたはずの「痛み」が溢れ出るような、詩的な表現を生み出している。
これは、難民という「他者の痛み」を、鑑賞者の皮膚感覚にまで引き寄せ共感を促す、強力な美学的戦略である。元カッセル芸術アカデミー学長兼教授 カーリン・ステンペル(Karin Stempel)の指摘する「穏やかな硬さ」は、悲嘆の記録でありながら、同時に、それらを乗り越え、未来へと歩もうとする人間の不屈の生命力をも象徴している。
《Being in the Face》シリーズは、写真のドキュメンタリー性、インスタレーションの空間性、そして物質の詩的メタファーを見事に融合させ、現代アートにおける「社会参加型芸術」の新たな領域を開拓したと言える。井上廣子は、難民女性たちの尊厳を守りながら、彼女たちの声と痛みを、私たち自身が直面すべき普遍的な問いへと昇華させたのである。

3F 展示
痛みの表面、希望の光—井上廣子が照らす“交差するまなざし”の倫理
井上廣子展「Being in the Face+交差するまなざし」は、現代アートが社会に対し、いかに深く、そして美的に介入できるかを示す傑出した展覧会である。ギャラリーの静謐な空間で私たちに対峙した難民女性たちの「顔」は、その眼差しと、ワックスの表面に刻まれた無数のクラックによって、私たちの記憶に深く刻み込まれた。
2Fの群像的なポートレートと『宙づりの小屋』が難民の「宙ぶらりんの状況」という構造的な問題を提示し、続く3Fのより大きなポートレートが、個々の女性の「心の深い傷」と「存在の主張」を、圧倒的なスケールで私たちに突きつけた。この展示構成は、井上廣子の芸術的洞察力の深さを示すものであり、難民というグローバルな問題に対する、最も情感豊かで、かつ鋭い批評的応答であると言える。
作家は、この大きな深い問題の根底に何があるのか真摯に向き合い、人間の歴史が「ロールバック」するような現代の分断に対し、写真と物質性をもって立ち向かった。彼女の作品が描き出すのは、悲劇や絶望だけではない。それは、痛みを抱えながらも決して諦めず、生きることを選び続ける人間の尊厳と、そこに見出される希望の萌芽である。井上廣子の芸術は、私たちに「交差するまなざし」を持つことの重要性、すなわち、他者の痛みを自己の痛みとして感じ、その存在に責任を持つことの倫理をうながす。現代社会において、彼女の活動は、難民という社会的弱者の尊厳を不動のものとする、その芸術的意義は計り知れない。
参考ページ
・井上廣子/Hiroko Inoue -Being in the Face + 交差するまなざし- – Yoshiaki Inoue Gallery (最終確認2025年10月30日)
・Hiroko Inoue 井上 廣子– Yoshiaki Inoue Gallery (最終確認2025年10月30日)
・井上 廣子 — AWARE-Archives of Women Artists Research&Eehibition- 日本 (最終確認2025年10月30日)
・Asian Women Artists:Gender/History/Border INOUE Hiroko (最終確認2025年10月30日)
