
Art Basel in Basel 2018 ©Art Basel
(※2018年6月執筆)
アート好きには言わずと知れた「アート・バーゼル」。1970年から始まったスイス北西部の都市バーゼルで毎年開催されている世界最大規模のアートフェアである。先日6月17日に第49回目のアート・バーゼルバーゼルが終了した。世界の290のトップギャラリーが参加、出品作家数4千人、メインのギャラリー会場では絵画、彫刻、写真、インスタレーション、パフォーマンスやビデオアートなどのジャンルから20世紀と21世紀の様々な話題のアーティストの作品が紹介され、来場者は約95,000人。この春3月開催のアート・バーゼル香港では約80,000人、去年12月にアメリカで開催されたアート・バーゼルマイアミでは約82,000人の来場者数であり、それぞれが単体で超大型イベントといえるだろう。このように本家本元のバーゼルだけでなく、香港、マイアミでも入場者数が格段に多い、そんな人気の高いアートフェアだが、実は閉鎖的な催しだというのはどれくらいの人が知っているだろうか。
「そんなに来場者が多いのに閉鎖的ってどういうこと?」と不思議に思うだろう。その理由を説明していこう。

Art Basel in Basel 2018 ©Art Basel 会場内の様子
アート・バーゼルは専門家とコレクターのためのもの
アート・バーゼルとはいったいどんな人たちで構成されているのだろうか。まずアーティスト、次にギャラリスト、アートコレクターである。作品を作る人、売る人、買う人がいて、アートマーケットが成立する。コレクターたちにとって世界で最も影響力を持つギャラリーがこぞって参加するアート・バーゼルはとても魅力的だ。参加するギャラリー名やメインとなる作家名は数か月前から順次発表されていく。そしてアート・バーゼルがアート・バーゼルたるのは、そこに「観る人」が加わるからである。ここでいう「観る人」というのは、すなわち主要な国際的芸術機関のトップや学芸員、世界的にも影響力が高い各種アート財団の代表やディレクター、国際的に活躍するキュレーターなどを指す。いわゆるアートの専門家たちだ。
実際、アートフェアが始まった直後に発表される速報(ニュースリリース)では、VIPプレビューで参加ギャラリーがどのような実績を上げたのか、どの所属のどんな人たちが足を運んだのかが必ず記される。彼らの参加は重要事項だからだ。この定期的に開催されている世界最大級のアートフェアは、世界中のアート関係者の社交の場ともなっており、アートのスペシャリストたちが会場に華を添えているのは間違いない。アート・バーゼルは本質的には専門家とコレクターたちのためのアートフェアなのである。


Galleria Continua Nedko Solakov Art Basel in Basel 2018 ©Art Basel
アート・バーゼルの厳しい参加基準
ギャラリーがアート・バーゼルに名前を連ねるのには高いハードルを乗り越える必要がある。発表はされていないが数百万円はくだらないフェア出展料、ほかにも作品の輸送費、宿泊代、交通費、食費、人件費などかかる経費は想像以上である。相当力のあるギャラリーで採算が合わなければエントリーすらも困難。その上、約300前後のフェア出展の枠に世界中から1000を超えるギャラリーの申込みが殺到し、参加するための厳しい選定基準が設けられている。毎年常連で参加しているギャラリーですら来年も参加できる確実な保証はない。だからこそアート市場において最高レベルのフェアといわれ、そこに参加することがギャラリーやアーティストたちにとってステイタスになり得るのだ。そしてその基準の高さはすべての参加者にとってフェアに対する大きな期待感につながっていく。

White Cube Ibrahim Mahama Art Basel in Basel 2018 ©Art Basel
参加できるのは招待されたアートコレクターのみ、このアートフェアには招待されたアートコレクターでないと参加できない。もう少しかみ砕いて言うと、アートフェアそのものへは料金さえ支払えば入場可能だが、もっとも重要なイベントはVIPと認められた人しかアクセス(入場)できないようになっている。VIPというのはもちろんアート作品を購入するアートコレクターたちのことである。
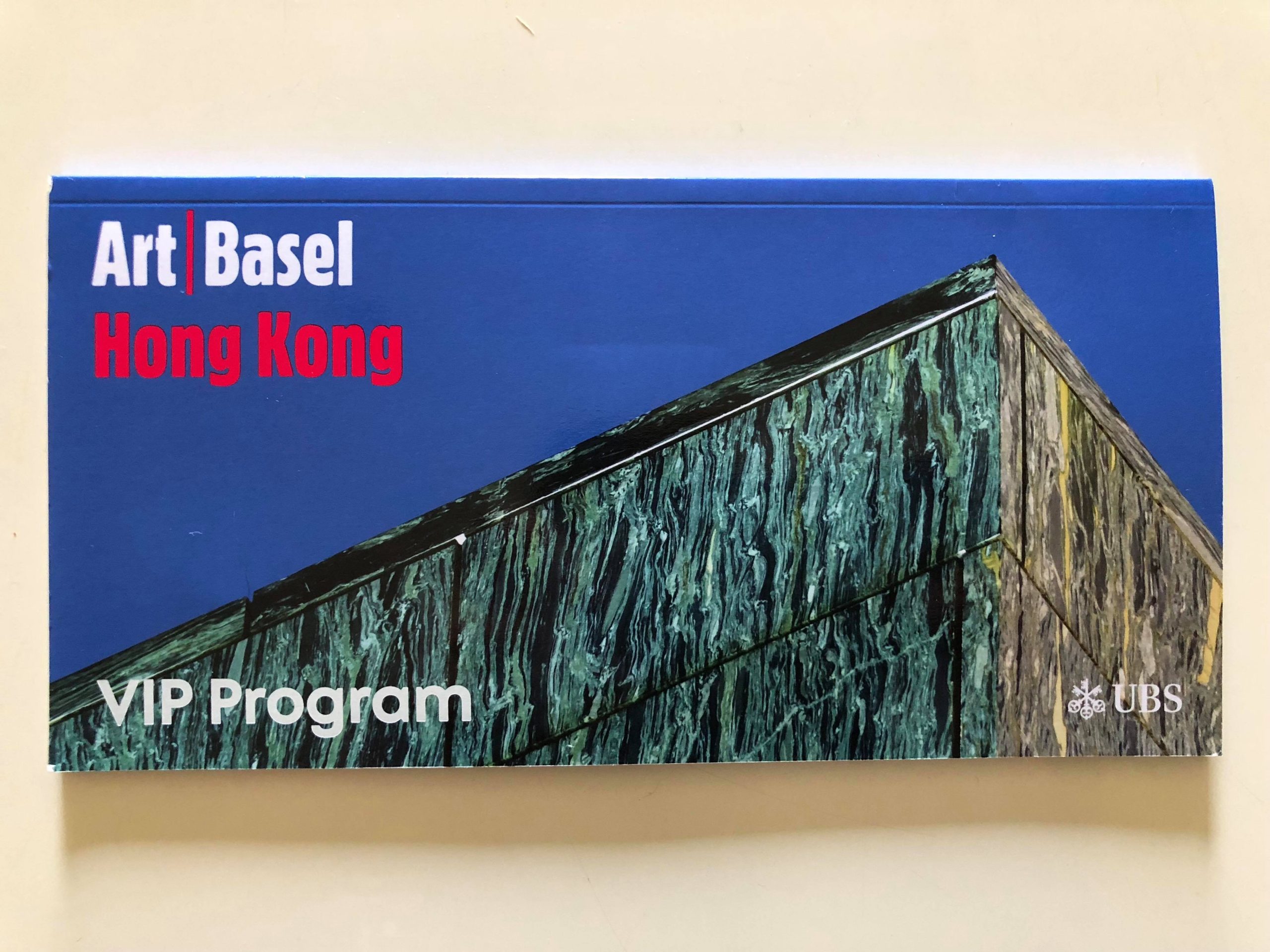
VIP Program Art Basel in Hong Kong 2018 様々なVIPプログラムが数多く記載されている。会場で入手可能。情報量が多いので参考になる。
アート・バーゼルともなればメイン会場だけでなく、期間中は地元のアート関連の施設、国際機関での様々な関連プログラムやイベントがあり、街中の主要ギャラリーなどでもオープニングやレセプションパーティなどが数多く開催される。そしてVIP限定の会場や催しも多々ある。主催者やギャラリーの立場からすれば、世界中から集まってくる有力なアートコレクターたちと接点を持つチャンスなのだから当然のことといえるだろう。
他にも会場内をゆっくり見るためのVIP専用の日程(プレビュー)や時間帯が組まれたり、コレクター専用のラウンジも用意されていたり、会場内のガイドツアーも毎日定期的に行われている。メイン会場から離れた場所でのイベントや展覧会へはVIPツアーが組まれ、シャトルバスが定期的に運行している。以上の3つが、アート・バーゼルが世界最大級のアートフェアでありながら閉鎖的である理由である。
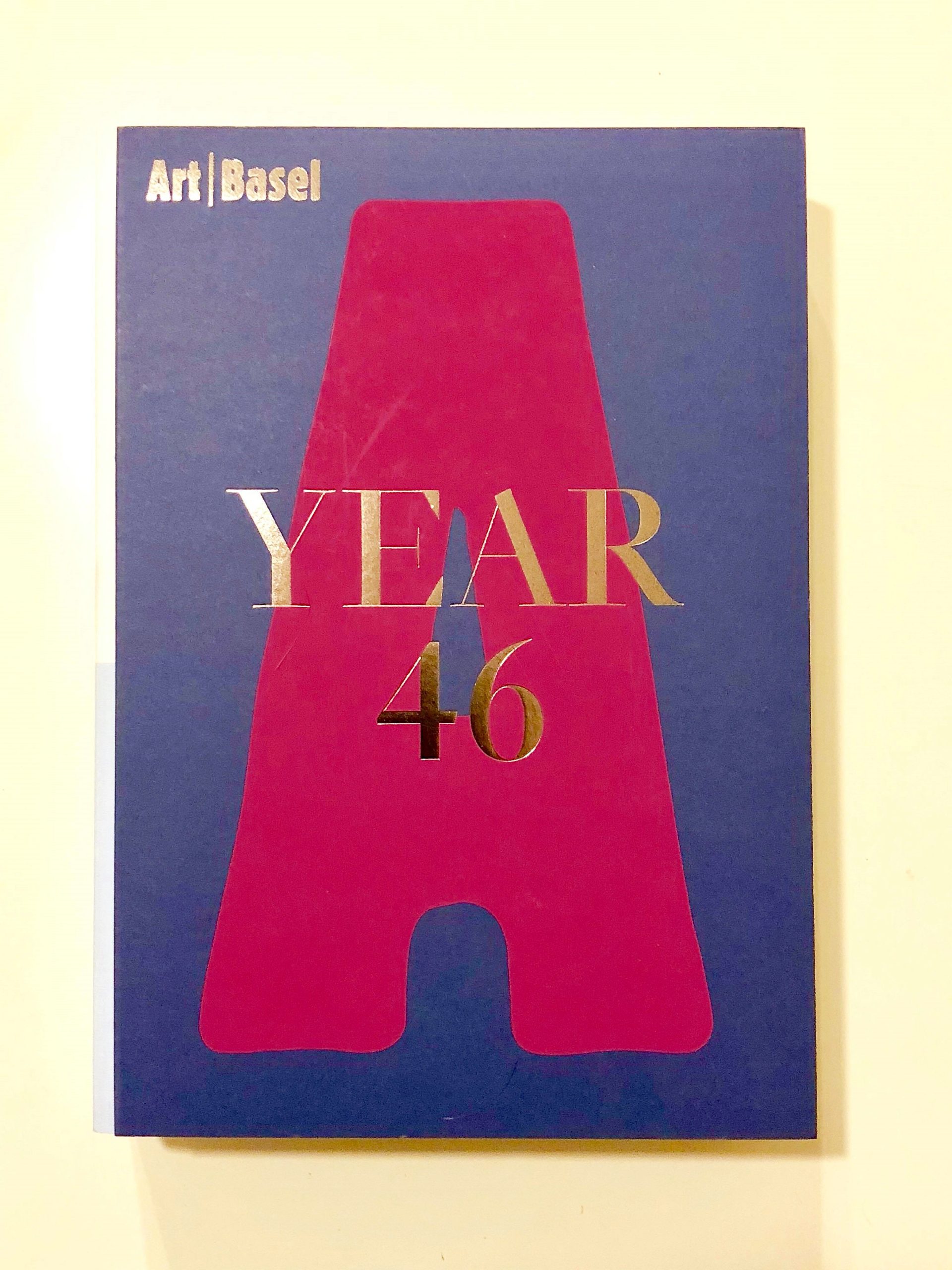
YEAR46は昨年2015年度当時のもの。VIPカードを所有者だけに配布。前年度の3会場のアートフェアの詳細や写真が掲載。A4サイズ、厚さ5.5cm、重さ2.8kg。購入すると約8,000円。(2025年現在は配布終了)

Metro Pictures Nina Beier Art Basel in Basel 2018 ©Art Basel
今年の春、3回目となるアート・バーゼル香港へプレスとして行ってきた。最初の頃は勝手がわからず、観ることだけで精一杯だったが、3回目にして、ようやく記者発表やレセプションにも参加するなど、回数を重ねたことで周囲の様子も見えるようになり、捉え方も随分と変化してきたところであった。
日本のアートフェアではメディア関係者に対してVIPと同等に近い対応をしてくれることが多く同じ感覚でいたのだが、アート・バーゼル香港では違っていた。誰がお客様なのかそうでないのか、もっとシビアな言い方をするとお金になるかならないか、その線引きがとてもハッキリとしている。メディア関係者への対応とアートコレクター(ギャラリーも主催者側にとっては顧客である)へのサービスは徹底して分けられていた。

neugerriemschneider Galleries 2018 Art Basel in Basel 2018 ©Art Basel
そもそも、宣伝しなくともどの会場も来場者は嫌というほど来るし、売上をあげていくのであれば来場者数を増やすよりもターゲットを絞っていく方が効果的なところまで来ているような成熟したアートフェアである。メディアの力は必要ないとはいわないが、期待されているのはこれから経済力を身に付け顧客になってくれそうな若い世代の潜在層への働きかけや長期的なブランド戦略といえる。
誰が来ても楽しめるアートフェアを目指したのではなく、誰を顧客とするのかをしっかり見極めてサービスを徹底的に追及した結果、現在のアート・バーゼルの地位を確立することができたのだ。確かに閉鎖的な要素も多分にもあるかもしれないが、例えVIPでなくても足を運びそこで得られる経験は計り知れないものがある。来年もアート・バーゼルへ行くかと聞かれれば答えは「YES」である。おりしも来年はアート・バーゼル50周年記念、またどんなアートフェアになるのか期待が大きく膨らむ。
初出 世界最大級のアート・フェアなのに、超閉塞的なアート・バーゼルのお話 | / ARTLOGUE(2018年6月18日)
_________________
➡本稿をもとに、さらに内容を掘り下げた新しい記事も公開しています。読み応えのある記事になっていますので、ぜひあわせてご覧ください。
アートバーゼル、その熱狂と静寂の裏側:世界最高峰のアートフェアを読む コラム 黒木杏紀評 | アート&ブックを絵解きするeTOKI
