「狩野智宏・神代良明展」@東京画廊
秋丸 知貴
2017年1月21日(土)– 2月18日(土)
東京画廊+BTAP https://www.tokyo-gallery.com/
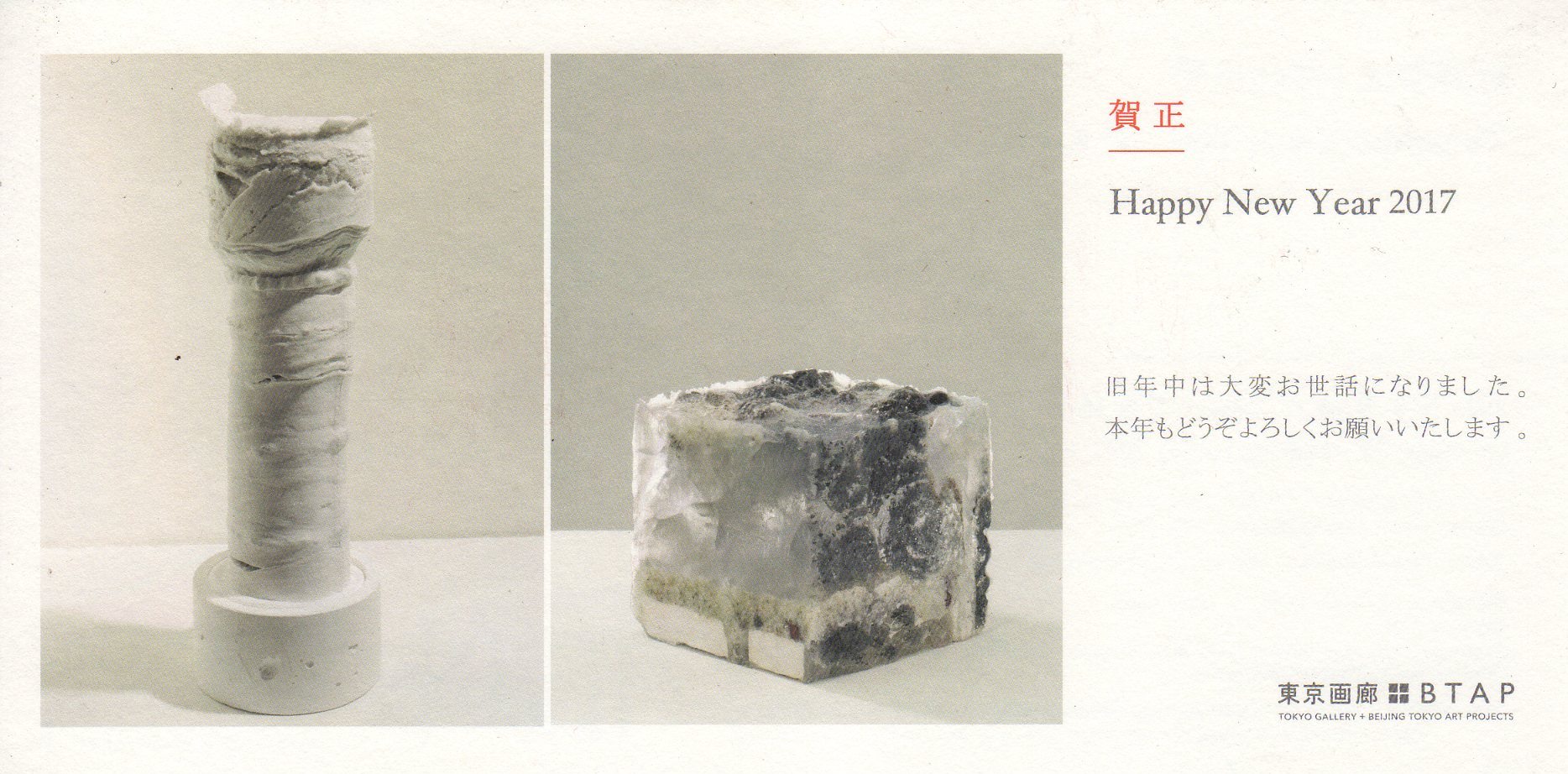
「自然(じねん)」と「のこり体」
狩野智宏と神代良明のガラス彫塑による「二人展」である。しかし、展示会場を一瞥した鑑賞者の多くは、この展覧会を「個展」と思ってしまうのではないだろうか。それほど、両者の作風にはどこか通じ合うところがある。少なくとも、私は初見ではそれぞれの作品がどちらの作家のものかすぐに言い当てることができなかった。
このことは、狩野と神代には制作手法、そしてその背後の制作理念に共通性があることを示唆する。この二人展を企画した東京画廊の着眼も、そこに関わるのであろう。実際に、開催趣旨文には「二人のコンセプトの底には、近代以前の日本人の自然観が残っています」と記されている。それでは、狩野と神代の作品に通底する「近代以前の日本人の自然観」とは一体何だろうか?
まず注目すべきは、狩野と神代が共にガラスを素材としている点である。よく知られているように、ガラス自体は日本では既に弥生時代から装身具の勾玉などで用いられていた伝統的な工芸素材である。しかし、「純粋鑑賞芸術(ファイン・アート)」つまり「美術」である彫塑の素材としては、ガラスは極めて新しいものである。西洋でさえ、ルネ・ラリックやエミール・ガレなどのガラス作家が表舞台に出たのは19世紀末のアール・ヌーヴォーの時代であり、しかもそれはまだ多分に「工芸」の領域内であった。西洋でも日本でも、ガラスが彫塑美術の素材として本格的に扱われ出したのは戦後も大分経ってからであり、現在でもまだ素材の主流であるとは言いがたい。
そうした言わば変則的な素材であるガラスを、狩野と神代が美術家であるにもかかわらず選択したのは、二人が共にいわゆる美術大学の彫刻科出身ではないことと無縁ではないだろう(狩野は日本画科、神代は建築科出身)。つまり、普通であれば彫塑美術の素材としては避けられがちなガラスを、先入観がないからこそ抵抗なく選び取れたと考えられるのである。それと同時に、両者が生粋の工芸科の出身ではないことも、ガラスという「用の美」に縁深い工芸的素材を「鑑賞の美」を表現する美術の分野で積極的に用いることに肯定的に働いたはずである。
しかし、狩野と神代の作品の共通性は、ただ単にガラスという同じ素材を使っていることだけに留まらない。より重要な点は、そのガラスを素材として両者が創り出している造形である。
一見して分かるように、二人の作品はどれも、一般に彫塑として想像される洗練された端正な形体ではなく、あまり整えられていない武骨な形体を示している。つまり、両者は共にガラスを用いながら、その通念的特徴である滑らかな透明性ではなく、逆にザラついた不透明性を提示している。それぞれの形体は、ところどころ歪み、ひび割れ、くすみ、焦げ付いている。外面は今塗り固められたばかりかまだ作業途中のようであり、その内部も土や砂利等の夾雑物が入り混じったり、気泡が乱雑に浮かんだりしている。そのため、それらは鑑賞用の彫塑というよりも、まるで打ち捨てられた廃材を連想させずにはおかない。しかし、それでもなおこれらのガラス作品は、やはり外観上は依然として審美的な鑑賞に応える石碑のような佇まいを保持している。そのことが、この一見粗雑な造りが実は繊細な入念さに基づいており、敢えて偶然のままに放擲されたような造形を示すために可塑性と硬質性を併せ持つガラスが素材として選択されたことを暗示している。
ここで狩野と神代のガラス作品に共通しているのは、一般的な意味での人為的な仕上げの否定である。より正確に言えば、ここで二人の作品に顕著なのは、人間が事前に頭で考えた形態を素材に厳密に当て嵌めるのではなく、素材自体から事後的に偶然生まれる造形をできるだけ生かそうとする姿勢である。これは、普通に思われているほど単純な問題ではない。少なくとも、西洋美術の正統な規範から言えば埒外の美意識である。なぜなら、西洋美術では伝統的に、人間が理性を通じて意図的に構想した理想的形態にこそ一義的価値があり、素材はそれを具現するための従属的で無価値な材料に過ぎないからである。
この制作観は、自然観に関わる問題である。つまり、西洋では基本的に人間の方が自然より優れており、低級な自然を高級な人為で完成させなければならないという信念がある。そのため、西洋の標準的な美意識は、あくまでも人間が着想した人為的形態通りに素材を強制的に統御することを高く評価する。これに対し、日本ではちょうどその反対に、基本的に自然の方が人間より優れており、あざとい人為は深遠な自然の働きが加わって初めて完成されるという信念がある。そのため、日本の伝統的な美意識は、人間が素材を支配的にコントロールするというよりも、素材から生まれる予期せぬ偶然を高く評価する傾向がある。
例えば、日本の伝統的な焼物では窯変が好まれる。つまり、多くの場合、焼成時に素材の土や釉薬や火炎の性質がもたらす偶然の効果は、余計なものとして排除されるのではなくむしろ本質的な構成要素として愛でられる。そうした窯変への愛着を示す典型が、極端な形体の歪みや色彩の滲みを楽しむ、17世紀初頭に成立した織部焼である。なぜ拉げた不格好なものを愛好するのかと言えば、そこには前提として人間を超える偉大な自然に対する敬慕があり、そうした人知を超越した自然の働きの強い現われをそれらの偶然の造形に感受するからに他ならない。すなわち、織部焼における変形は自然美なのである。
こうした素材から自ずと生まれる偶然の作用を味わう日本の織部焼と好対照をなしているのが、西洋白磁のマイセンである。元々マイセンは、先に中国や日本で発達していた白磁への渇望から、土質が白磁に適していなかったヨーロッパで18世紀初頭に開発されたものである。そのため、ありのままの土質を生かすというよりも、白い素地を人為的に精製するために素材の徹底した科学的な分析と調合から出発している。つまり、マイセンの純白さは人工美であり、自然本来の偶然の作用をできるだけ人為的に排除した成果なのである。
このように、自然観の違いから制作観や美意識の差異が生まれ、西洋の端正な人工美と、日本の不均整な自然美という異なる二つの方向性が成立したと言える。この二つの方向性は、どちらが良くてどちらが悪いという二者択一のものではない。どちらの方向性も有益で必要であり、両者のバランスが取れることこそが望ましい。それはちょうど、織部焼とマイセンのどちらか一方だけしかないよりも、時と場合によりどちらも自由に利用できる方が生活がより豊かになることを想起すれば分かる。
しかし、現代ではあまりにも西洋的自然観だけが一方的に強まり、その人為による過剰な自然支配が、もはや人類の存続さえ危ぶませるほど致命的な公害や自然環境破壊を発生させている。そうした危機的状況下では、やはり自然を謙虚に敬愛する日本的自然観を再評価し、改めて両者のバランスを取ることが急務なのではないだろうか。少なくとも、東日本大震災以後、人間が自然を完全にコントロールできると考えるのは幻想であるという認識が広がり始めている。ここにおいて、日本の伝統的自然観を反映し、自然との調和的協働を表象する美術作品は、これまで西洋型近代文明が強力に推進してきた人間中心主義的な自然支配とは別の方向性があることを示す理念的指標になりうる。

こうしたアクチュアルな芸術主題に、狩野は「自然(じねん)」という言葉をキー・ワードにして取り組んでいる。この「自然」に「じねん」とルビを振る読み方は、西洋語の「ネイチャー(nature)」が人間に支配されるべき対象という含意を持ち、その翻訳語として「しぜん」という新しい読み方が明治時代以後に定着する前に用いられていた古語である。つまり、狩野は「自然(じねん)」という言葉を手掛かりとすることで、この古語に込められていた日本の伝統的自然観をもう一度追求しようとするのである。
様々な素材を高温で鋳込み、人為を超えてその本性・性質が自ずと顕現し、あるがままに存在する状態そのものを導く。例えば、ガラスを土・砂・石・鉄・石膏(硫酸カルシウム)という自然素材と共に焼成して、自ずから生じるひび割れや焼け焦げを風合いとして生かすことなどはその一つの実践である。もちろん、この場合も狩野のガラス作品はただ単に自然任せなのではない。そうではなく、素材が自ずから生み出す偶然を的確に補助する確かな技術に裏付けられた、作家と自然の協働の産物なのである。そして、狩野は自らの作品にこの「自然(じねん)」と同様の語義を持つ古代ギリシャ語の「ピュシス」の名称を与えている。このことは、こうした自然崇敬的な自然観はただ日本だけに限られるのではなく、古来人類全体に普遍的に共有されており、むしろ近代において強化された西洋的自然観こそが特異なのではないかという思想的な問題提起となっている。
興味深いことは、狩野の母方の曽祖父が日本画家の狩野友信であることである。周知のように、友信は江戸幕府の御用絵師の浜町狩野家の出身で、幕末明治期に川上冬崖やチャールズ・ワーグマンに西洋画法を学ぶと共に、アーネスト・フェノロサ、岡倉天心、狩野芳崖、橋本雅邦らと協力して廃れかけていた日本画の復興に精力的に取り組んだ、東京美術学校の創立教員の一人である。つまり、文明開化期に新たに西洋美術を翻案して「美術」概念が成立し、その残余概念として形成された「工芸」が美術の下に位置付けられ始めていた脱亜入欧の時代に、何とか日本画を工芸から美術へ高めようと尽力した代表的な功労者の一人と言える。その子孫である狩野が、工芸的な素材であるガラスを用いて美術作品で伝統的な日本的自然観を表象しようとしていることは、四代越しの和魂洋才の「アート・プロジェクト」として非常にユニークな歴史的・文化的価値も持っていると言えるだろう。
また、神代のガラス作品にも同様の問題意識が込められている。神代のキー・ワードは、「のこり体(Remaining composition)」である。この造語は、神代が半年間ほど机の上に置いていた蜜柑が萎びていく様子を観察した経験が基になっている。この時、蜜柑は次第に水分を失い静かに変色しつつ凝縮していった。そして最後に残った黒ずんだ小さな塊に、神代はある一つの確かな価値を直観する。つまり、こうした蜜柑の「のこり体」の成立過程には一定の自然な道筋があり、それはある意味で絶対的かつ不可逆的である。そこでは、普段は意識されることのない、存在を存在たらしめている、時間の経過や、重力の働きや、物質の性質などの人為を超えた自然の諸作用が構造的に顕現するのである。
そして、神代にとってガラス作品とは、その作品名「Remaining composition」が示すように、この表層的日常の深奥にある世界の本質的構造を知覚させる「のこり体」としての蜜柑の象徴的対応物である。つまり、ガラスを加熱する行為自体は人為的であるけれども、自ずから液体的に溶解し、自ずから重力と物質的性質により変形し、やがて自ずから固体的に凝結するガラスは、媒体として不可視の大自然の摂理を如実に実感させずにはおかない。そして、やはりこの場合も、神代のガラス作品はただ単に全てを自然に任せるのではなく、そうした自然の働きの痕跡をできるだけ確実に留める技術に裏付けられたものなのである。「物質と熱と重力とで成っていく構造を見届けつつ在らしめたい」という神代の発言は、正にこの意味で理解できる。
このように、狩野と神代のガラス作品には、通常の意味での人為的な仕上げを慎み、自然の諸作用から生まれる多様な表情をできるだけ生かすという共通性を観取できる。そして、作家が素材の支配者ではなく補助者となり、ただ単に作家が脳内で拵えた造形的着想を具現するのではなく、確かな手業を通じて作家と自然の協働というより高次の芸術的コンセプトを実現しようとする点にこそ、人間と自然を分け隔てずに根源的に一体であると感受する、二人の作品に通底する「近代以前の日本人の自然観」を指摘できるだろう。
