
芦屋五市立美術博物館「具体美術協会と芦屋、その後」 会期:2025年7月5日(土)―8月31日(日)
【ARTS STUDY 】
◾️「具体」再考 第2回
「具体」と万博-その光と影ー:第2部 「具体」にとって大阪万博とは
日時:2025年9月5日㈮ 19:00〜20:30
講師:平井章一(関西大学文学部教授)
会場:BARまどゐ
今年は大阪で55年ぶりに万博が開かれています。前回の1970年の大阪万博では、高度経済成長時代を背景に、テクノロジーに支えられた便利で豊かな近未来像が提示され、その具現化に多くの美術家が参画しました。地元関西で新しい美術を切り開いてきた具体美術協会(「具体」)もまた、意地を見せるかのように、パビリオンでの展覧会だけでなく、太陽の塔の裏側にあった「お祭り広場」で壮大なイベントを開催しています。「具体」は、このあとまもなくしてリーダーの吉原治良の急死により解散しますので、大阪万博は結果的に「具体」の活動のフィナーレを飾る場となりました。
第2部では、これら語られてこなかった大阪万博の「影」の部分に目を向け、光と影を併せ見ることにより、「具体」というグループの本質について考えてみたいと思います。
芦屋から万博へ — 「具体」が描いた戦後日本美術の軌跡
はじめに — 知る、見る、歩く、話す。アートと「つどう」新しい学びの場【ARTS STUDY】
アート作品の多くは、その土地の光や風、歴史のざわめきの中で生まれる。しかし私たちは、その背景から切り離され、白い壁に囲まれた静かな空間で作品と対峙することがほとんどだ。もし、作品が生まれた場所へ自らの足で赴き、アーティストが見たであろう風景を眺め、専門家や仲間との対話を通じてその物語を立体的に知ることができるとしたら。五感をフル活用するそんな「探求」は、アートの全く新しい扉を開いてくれるに違いない。
神戸で30年以上にわたり、アートを媒介としたユニークな活動を続けてきたC.A.P.(特定非営利活動法人 芸術と計画会議)が手がける【ARTS STUDY】は、まさにそんな新しいアートとの出会いを提案するプログラムだ 。これは「アートの学びとつどい」をテーマに、半年という時間をかけて様々な角度から一つのテーマをじっくりと深掘りしていく継続的な学びのコミュニティである 。単発の講座では味わえない、参加者同士の交流から生まれる化学反応や、回を重ねるごとに深まっていく知識と体験。それは、専門家による座学、現地でのフィールドワーク、そして仲間との対話が組み合わさった、実に「立体的」な学びの場なのだ 。アートをきっかけに人が集い、知的好奇心がスパークする、大人のための最高に刺激的な「部活動」と言えるかもしれない。

前回【ARTS STUDY 2024】の講座の様子
2025年8月24日、その一回目となる講座が開講された。テーマは「『具体』再考」。戦後日本を代表する前衛美術グループ「具体美術協会」を多角的に学ぶ、半日にわたる3部構成のプログラムだ。関西を拠点とした「具体」の活動の舞台である芦屋を実際に歩き、作品と対話し、専門家の解説に耳を傾ける。本稿では、五感で「具体」を体験する、この濃密な一日の記録を報告する。
「破壊から創造へ」戦後日本が生んだ革命的アート集団・具体美術協会とは
まず、「具体」とは何かについて触れておかねばならない。1954年、吉原治良をリーダーに芦屋で結成された具体美術協会は、戦後日本の、ひいては世界の美術史にその名を刻んだ前衛美術グループである。彼らのスローガンは「人の真似をするな、今までにないものをつくれ」。この言葉通り、従来の絵画や彫刻の概念を根底から覆す、過激で実験的な試みを次々と発表した。
その活動は常識破りの連続だった。田中敦子は色とりどりの電球を身にまとった「電気服」でパフォーマンスを行い、村上三郎は重ねたクラフト紙のスクリーンに体当たりして突き破った。白髪一雄は天井から吊るしたロープにぶら下がり、足で描く「フット・ペインティング」を創出し、嶋本昭三は絵具の瓶をキャンバスに投げつけることで作品を完成させた。
彼らは「美術」という枠組みそのものを問い直し、「創造とは何か」を根本から探求した。特筆すべきは、完成した作品だけでなく、制作の「行為」そのものをアートとして提示した点であり、これは現在の「パフォーマンス・アート」の先駆けとなる革新的な発想だった。その衝撃はすぐに海外へ伝播し、フランスの美術評論家ミシェル・タピエに絶賛され、国際的な評価を確立した。
彼らの背景には、戦争で価値観が根底から覆された日本社会への深い問題意識があった。新しい時代にふさわしい表現を模索する姿勢は、戦後日本の若者たちの心情を代弁していたと言える。1972年に活動を終えたが、その精神は今なお多くのクリエイターにインスピレーションを与え続けている。
第1部|【芦屋遠足編】「具体」の聖地を歩く — 現在に息づく前衛精神の記憶
私たちのフィールドワークは、関西大学教授の平井章一氏(以下、平井先生)の先導のもと、JR芦屋駅から始まった。

2025年8月24日(日)JR芦屋駅集合! 【ARTS STUDY 2025】開講
革新的建築空間から始まる物語 — 芦屋市民会館ルナ・ホール
最初に訪れたのは、1970年開館の芦屋市民会館ルナ・ホール。建築家・山崎泰孝が35歳の若さで設計した建築だ。

RENAISSANCE CLASSICS 芦屋ルナ・ホール
ここで特筆すべきは、吉原治良が「空中に絵を描きたい」と語り制作したホワイエの壁画である。黒を基調とした空間に、床・階段・天井を貫いて白い線が走り、観客が特定の視点に立つと一つの直線として浮かび上がる。建築と一体化した環境表現は、平面絵画を超えて空間そのものを体験させる具体的実践の象徴といえる。

芦屋ルナ・ホール内部。この日は講演会があり中には入れずガラス越し。階段の白い線が作品の一部分
山崎はまた、中之島にあった「具体」の拠点、グタイピナコテカの代替施設として130mの巨大なタワー型美術館の設計も任されていたという。この幻の計画は、「具体」が見ていた壮大な夢の大きさを物語っている。

炎天下にも関わらず、平井先生による芦屋ルナ・ホールの説明を熱心に聞く参加者たち
・革新的な芦屋ルナ・ホール|具体フィールドミュージアム
・グタイピナコテカ|具体フィールドミュージアム
・二つあった新グタイピナコテカ構想|具体フィールドミュージアム
晩年の住まいと創作の記憶—吉原治良邸跡
次に、吉原が最後の4年間を過ごした邸宅跡を訪れた。現在はマンションになっているが、かつてここには黄色い強化プラスチックの門を持つ個性的な邸宅があった。ここが万博を巡る議論も交わされた、後期の重要な拠点のひとつであったことが窺える。
「具体」創作の聖地—自宅とアトリエ跡
最も重要な場所が、1926年から1968年まで吉原が住んだ公光町の自宅とアトリエ跡だ。この場所こそが「具体」の活動拠点だった。メンバーは自作を携えて頻繁にこのアトリエを訪れ、吉原の指導を仰いだ。庭で作品を並べ、メンバーたちが吉原を囲んで議論する写真も残されており、ここが創造のエネルギーに満ちた場所であったことを物語る。
新人発掘の場 — 芦屋市立精道小学校の講堂跡と芦屋公園
芦屋市消防署のある場所には、かつて精道小学校の講堂があり、毎年開催される芦屋市展は「具体」メンバーの登竜門となっていた。吉原はここで有望な若手作家を発掘し、グループに勧誘した。

芦屋市立精道小学校前にて。看板より右側に講堂(現・芦屋市消防署)があった。
続いて向かった緑豊かな松林が美しい芦屋公園。ここで「具体」は、美術館という制度的なハコを飛び出し、青空の下で2度にわたり野外展覧会を開催した 。その名も「真夏の太陽にいどむ野外モダンアート実験展」(1955年)と「野外具体美術展」(1956年)。当時の写真には、奇妙なオブジェの周りに海水パンツ姿の海水浴客や潮干狩りを楽しむ家族連れの姿が写りこんでいた。
アートが一部の専門家のものではなく、人々の日常の中に開かれていた自由な時代。その開放的な空気感が、公園の松林を吹き抜ける風から感じられるようだった。炎天下の中、日傘を差しながら平井先生の話に夢中で耳を傾ける参加者たち。ただの街歩きではない。過去の芸術家たちの息遣いを追いかける、知的なタイムトラベル。これこそが【ARTS STUDY】の醍醐味である。

芦屋公園 松林

芦屋公園の松林を抜けていく。まさにこの場所で「野外具体美術展」が開催された
・国鉄・阪神電鉄の開通とリゾート開発|具体フィールドミュージアム
第2部|【芦屋市立美術博物館 大槻学芸員 トーク&展覧会鑑賞編】 具体の精神を受け継ぐ芦屋の文化的気概
フィールドワークの終着点である芦屋市立美術博物館では、学芸員の大槻晃実氏(以下、大槻学芸員)によるトークが行われた。

芦屋市立美術博物館
芦屋市立美術博物館の確かなコレクション基盤
1991年に開館した同館は、「具体」のコレクションにおいて、初期から後期までを包括的に収集している点で世界的に見ても重要な役割を担っている。現在開催中の展覧会「具体美術協会と芦屋、その後」は、第一部で「具体」18年間の軌跡を、第二部では万博準備期以降の動向と、解散後の芦屋への影響を検証する構成となっている。
1992年の野外具体美術展 再現プロジェクトの感動的エピソード
大槻学芸員が語った最も印象的なエピソードは、1992年の野外展再現プロジェクトに関するものだ。この再現展を訪れた一人の女性が、「1955年の野外展も見た。あの時、戦後日本がやっと自由になれたと感じた」と語ったという。この証言は、「具体」が単なる美術運動ではなく、戦後日本の精神的解放の象徴として人々の記憶に刻まれていることを示している。
芦屋川国際ビエンナーレとルナ・フェスティバル
「具体」解散後も、その精神は芦屋に根付いていた。1972年と74年には「芦屋川国際ビエンナーレ」が、75年には「ルナ・フェスティバル」が開催され、当時の最先端の芸術家たちが集った。これらは、「具体」が蒔いた種が、芦屋という土壌で新たな文化活動として花開いたことを示す好例である。
・「具体」が駆け抜けた時代、その精神が芦屋に刻んだもの ー「具体美術協会と芦屋、その後」 芦屋市立美術博物館 展覧会レビュー

元永定正 《液体(赤)》1956年 / 2025年 真夏の太陽にいどむモダンアート野外実験展(1955年7月) 撮影:ERINA YASUKAWA
第3部|【平井先生 講演編】1970年大阪万博 — 「具体」が描いた未来の万華鏡
一日の締めくくりは、再び平井先生による講演。1970年の大阪万博における「具体」の活動を詳細に解説した。「具体」の万博参加は1968年4月頃から具体化し始め、上前智祐の日記や吉原の秘書的な役割も担っていた吉田稔郎のノートには、この時期から万博関連の打ち合わせが頻繁に記録されているという。
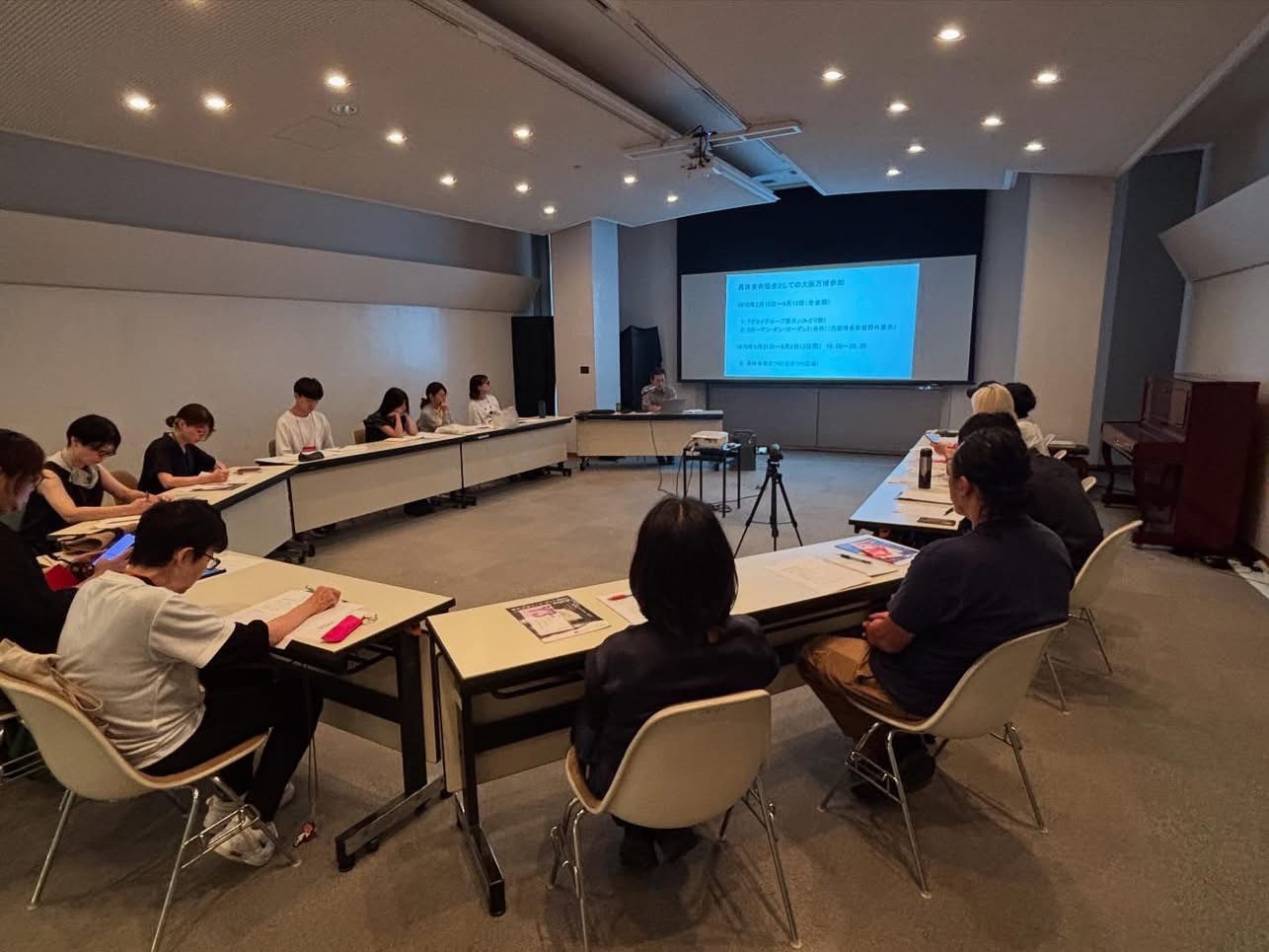
第3部、平井先生の講演の様子
光と影を宿す三つの舞台 — 具体の万博参加概要
「具体」が万博で参加した主要な催しは3つあった。会期中のみどり館の「グタイグループ展示」と屋外合作「ガーデン・オン・ガーデン」、そして会期末の3日間に開催されたパフォーマンス「具体美術まつり」である。
1)みどり館 — 最後のグループ展示
「みどり館」の展示の目玉は「アストロラマ」という全天全周映画で、天井のドーム全体に映像を映し出すシステムだった。総合プロデューサーは大林組の大林芳郎、脚本は谷川俊太郎、音楽は黛敏郎が手掛け、そして全体の美術コーディネートを吉原治良が「エントランスホール展示企画監修指導」として担当した。3月15日から9月13日までの全会期にわたって開催された展示では、メンバーが電気仕掛けで動く作品が多数含まれていたことで、当時の最新技術を用いた作品を展示していた。吉原治良をはじめ、村上三郎、今井祝雄、大原紀美子、小野田實、上前智祐、白髪一雄、名坂有子、吉田稔郎など具体の主要メンバーが参加し 結果的に、これが「具体」として会員全員が作品を並べた最後のグループ展となった
2)ガーデン・オン・ガーデン — 関西代表としての合作
万博美術展の企画の一つとして、「関東対関西の文化的競演」という趣旨のもとに関東チームと関西チームのアーティストがそれぞれ合作を出品する催しがあった。関東側は美術評論家の東野芳明を中心とする「ホーム・マイ・ホーム」という作品で、ネオダダイズム・オルガナイザーズの吉村益信がコーディネーターを務めた。
いっぽうで、関西代表として具体が選ばれ、14名のメンバーが一つの作品を共同制作した。プロデュースは吉原治良、構成は白髪一雄が担当した。かまぼこ型の大きなモルタルのオブジェをベースに、各メンバーが様々な要素を加えていく共同制作形式だった。制作過程は映像作家クリスチャン&マイケル・ブラックウッドによってドキュメンタリー「ジャパン・ザ・ニューアート」として撮影されたこの制作過程はドキュメンタリー映画として記録され、彼らの共同制作の様子を今に伝えている。
3)具体美術まつり — 未来への最後の花火
万博のハイライトとなったのが、お祭り広場で開催された「具体美術まつり‐EXPO‘70 お祭り広場における人間と物体のドラマ」だ。お祭り広場を覆う大屋根は建築家、丹下健三氏の代表作の一つで、東西108メートル、南北291.6メートルに及び、重さは約5000トンという壮大な空間だった。
制作・プロデュースは吉原治良、構成は白髪一雄、演出は元永定正、演出補佐は嶋本昭三と村上三郎が担当した。8月31日から9月2日までの3日間、夜19時から20時20分まで約1時間20分に及ぶ催しには10個の出し物が含まれていたが、個人名は一切表示されず、「具体」のグループとしての出し物として統一されていた。
平井先生は当時の記録写真と白髪一雄の台本に描かれたスケッチなどと併せてプログラムの内容を一つ一つ丁寧に紹介し、また実際には行なわれなかったプログラム案についてもそれらの資料から紹介する。巨大なバルーンが空を舞い、スパンコール人間が踊り、101匹の犬のぬいぐるみが大行進し、音楽のなま演奏もある奇想天外な出し物は、最後は消防車から大量の泡が噴射され、出演者も観客も泡まみれになるという祝祭的なクライマックスを迎えて終演する。
これまで映像や一部の資料展示だけだはその全容の把握が難しかった「具体美術まつり」の内容を平井先生はわかりやすく丁寧に説いてゆく。このパフォーマンスは、技術と芸術の融合による新しい表現の可能性を示したが、皮肉にもこれがグループとしての最後の大きな輝きとなった。
・宇宙時代の美術「阪神パーク」と「具体」|具体フィールドミュージアム
・万博と「具体」|具体フィールドミュージアム
記憶の地層から未来への創造へ — 現代に息づく前衛精神の継承
今回のプログラムを通じて私たちが体験したのは、単なる史跡見学ではない。「具体」という運動の本質への深い洞察だった。芦屋という文化的土壌が「具体」を育み、「具体」が芦屋に与えた刺激が新たな文化を生んだ。この相互作用の中にこそ、アートが社会に与える真の意味を見ることができる。現在は住宅地となった場所に眠る記憶の地層から、戦後日本美術史における「具体」の革新性と、芦屋という土地が持つ文化的な豊かさを再発見する貴重な機会となった。
【ARTS STUDY 2025】 講座レポートVol.2/「具体」再考1-②はこちら
【ARTS STUDY 2025】特設サイト
