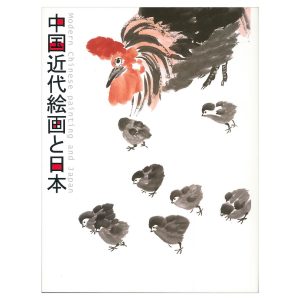
十九世紀後半から二十世紀前半の約一〇〇年の近代中国絵画の展開を、「伝統」と「近代」という時間軸と、「東洋」と「西洋」という空間軸に基づき、日本との交流という観点から概観する、「中国近代絵画と日本」展が京都国立博物館で開催された。
展示内容は、南京総領事等を務めた外交官・須磨弥吉郎が、一九二七(昭和二)年から一九三七(昭和一二)年までの中国在勤中に収集し、京都国立博物館に寄贈した「須磨コレクション」を核とし、近代中国画壇で活躍した呉昌碩、斉白石、高剣父、黄賓虹、張大千、徐悲鴻、劉海粟など、国内外の約二〇〇点の優品で構成されていた。
概略すれば、日中両国にとって「近代」は、アヘン戦争と黒船来航に象徴される欧米列強の東アジア進出から始まる。圧倒的優位を示す近代西洋の合理主義精神と科学技術文明への対応は、中国よりも日本の方が早かった。日本が和魂洋才を唱え、明治維新を通じていち早く西洋型近代国家へと発展するのに対し、中国は中華思想からの脱却が遅れ、戊戌の変法の失敗等により政治・社会・経済面で長らく低迷する。
文化・芸術面でも、当初特に絵画では、日本が西洋の「アート」の翻訳概念としての「美術」を積極的に推進したのに対し、中国は伝統的な文人の教養である詩書画としての「筆墨」を保守する傾向が強かった。しかし、中国も次第に西洋的近代化の波に洗われる中で、「筆墨」から「美術」への革新が目指される。そのとき中国が、留学や視察等を通じて、画法・美術史・美術制度等の多くの面で参考にしたのが、先行する日本であった。
画法では、日本における「(西)洋画」と「日本画」と同様に、中国でも西洋画材を用いる「西画」と伝統画材を用いる「国画」が成立し、特に伝統的な水墨画に西洋的な立体感や空間表現を取り入れる「新国画」には、西洋的写実を消化した円山四条派の流れを汲む京都画壇の竹内栖鳳や山本春挙等の影響が大きかったことが、実作品の比較展示により明瞭に示されていた。
また、中国が一方的に日本に学んだのではなく、日本もまた、西洋化を進める過程で、東洋の文人的伝統を中国から積極的に受容しており、近代日中の国際交流が双方向的であったことが、富岡鉄斎を巡る人間関係等で明確に提示されていた。
こうした近代中国絵画を紹介する展覧会が国立博物館で開催される背景には、昨今の中国の急速な台頭があることは間違いない。展覧会内容における西高東低を脱し、従来知られていなかった中国との歴史的・文化的交流に光を当てた点で、本展を高く評価したい。
本展でもう一つ特筆すべきは、須磨弥吉郎が、作品のほとんどを当地の画家や政治家達との交友によって入手している点である。人間的な魅力を備え、確かな審美眼を持ち、内外新旧の文化や芸術を正しく評価できる、真の「文人」外交官、さらには真の「文人」政治家の登場を待ちたい。
神戸市立博物館 二〇一一年一二月一〇日~二〇一二年一月二二日
京都国立博物館 二〇一二年一月七日~二〇一二年二月二六日
※秋丸知貴「展覧会評 中国近代絵画と日本展」『日本美術新聞』2012年3・4月号、日本美術新聞社、2012年2月、21頁より転載。
