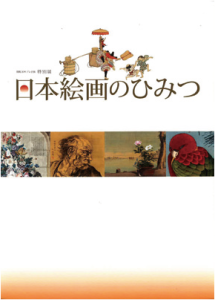
神戸市立博物館 2011年12月10日~2012年1月22日
日本近世の画家達がどのように絵画を作り上げていたかを「ひみつ」と捉え、形態・技法・素材の多角的な観点からその特質と魅力に迫る、「日本絵画のひみつ」展が神戸市立博物館で開かれた。
本展は、同館の開館30年プレ企画特別展であり、所蔵する異国趣味美術を収集した「池長孟コレクション」を中心に、関連作品105点が展覧された。
本展の核心は、16世紀の南蛮貿易時代以来、日本がいかに西洋美術の影響を受容してきたかを辿ることにある。特に、明治以後に西洋の「アート」概念を摂取し、展覧会や美術学校等の美術制度が確立される中で、「(西)洋画」に対する新ジャンルとして「日本画」が成立し、それ以後の近代的な「日本画」がどのように西洋化されたか、またそれ以前の伝統的な「日本画」様式がどのように忘失されたかを再考するものであったと言って良い。
形態面では、日本の伝統絵画は住環境に合わせて、掛軸、巻子、屏風、衝立など様々な形式を持ち、時には対幅・一双等の複数で一作品と数えられ、画中の賛や落款もまた重要な構成要素であることが、河村若芝《寒山拾得図》や狩野内膳《南蛮屏風》等で示されていた。また作品は、絵自体だけではなく表具と併せて初めて完成するものであり、表装が作品鑑賞に大きく反映することが《泰西王侯騎馬図》等で紹介されていた。
技法面では、日本近世の画家達は、全くの独創ではなく先行する本画や粉本の模写から制作を始めるのが一般的であることが、雪村周継や狩野探幽等の実例で表されていた。また、その手本は中国や西洋にも大いに求められており、本展の中心画家ともいえる江戸時代の秋田蘭画の佐竹曙山・小田野直武や、洋風画家の石川大浪・谷文晁等が、鎖国という情報の限定された時代にいかに精力的に西洋的写実画法を消化し新たな作品へと昇華したかが、実際に参照した原本と数多く比較されていた。
素材面では、伝統的な日本画では、鮮やかな立体表現を行う際には裏彩色が行われていたが、西洋美術の感化でより明るく華やかな最新の色材が追求されたことが、曙山《椿に文鳥図》や直武《不忍池図》のプルシアンブルー及び、狩野芳崖《仁王捉鬼図》の合成顔料等に指摘されていた。また、明治30年代以降の近代的な日本画では、人造や天然の新しい岩絵具も開発され、展覧会用や洋風建築の壁画用に額装の大画面が志向されるにつれて、絵絹に替わり巨大和紙が普及したことも説明されていた。
本展が多様な作品を通じて示す重要な意義は、西洋美術の輸入は非常に長い歴史を持ち、明治以後に限ってもそれ自体が既に新たな日本絵画の伝統を形成しているという事実である。その意味で、当然明治以後の近代的な「日本画」は正統な日本の伝統絵画として評価されるべきである。しかし同時に、明治以前の伝統的な「日本画」が持つ豊潤な奥行きもまた決して忘却されるべきではないだろう。そこにこそ、新たな伝統の土壌となる「日本絵画のひみつ」が隠されているのではないだろうか。
※秋丸知貴「展覧会評 日本絵画のひみつ展」『日本美術新聞』2012年3・4月号、2012年2月、日本美術新聞社、21頁より転載。



