
会場「BARまどゐ」入口
【ARTS STUDY 】
◾️「具体」再考 第1回
「具体」と万博-その光と影ー:第1部 大阪万博での展示と「具体美術まつり」+ARTSの遠足@芦屋の「具体」ゆかりの地+芦屋市立美術博物館
日時:2025年8月24日㈰ 11:45〜16:30 JR芦屋駅集合
講師:平井章一(関西大学文学部教授)
今年は大阪で55年ぶりに万博が開かれています。前回の1970年の大阪万博では、高度経済成長時代を背景に、テクノロジーに支えられた便利で豊かな近未来像が提示され、その具現化に多くの美術家が参画しました。地元関西で新しい美術を切り開いてきた具体美術協会(「具体」)もまた、意地を見せるかのように、パビリオンでの展覧会だけでなく、太陽の塔の裏側にあった「お祭り広場」で壮大なイベントを開催しています。「具体」は、このあとまもなくしてリーダーの吉原治良の急死により解散しますので、大阪万博は結果的に「具体」の活動のフィナーレを飾る場となりました。
第1部では、そうした展覧会やイベントを記録写真、映像などで仔細に検証し、「具体」が大阪万博で表現しようとしたものとは何だったのかを振り返ります。一方で、当時の美術家がもろ手を挙げて大阪万博に賛同したわけではありませんでした。時は学生運動まっさかり。若い美術家たちを中心に、国家主導の近未来のイメージづくりに美術家が加担することへの反対運動があり、「具体」のなかにも彼らの意見に密かに共鳴するメンバーがいました。また、それまで経験したことのない規模の展覧会やイベントは、「具体」の基盤をゆるがす問題ももたらしています。
大阪万博の熱狂と「具体」の選択―【ARTS STUDY】で紐解く光と影
アートを学び、人とつどう場所
アートは専門家だけが語る高尚なもの―。そんなイメージを覆す学びの場が、神戸で始まった【ARTS STUDY 2025】だ。ここはアートを切り口に歴史や社会を学び、多様な人々が自由に対話を楽しむための開かれた学び場である。半年間にわたる講座では、アーティストや研究者と共に考えることで、私たち自身の視点を豊かにしてくれる。
2025年9月5日に開催された第2回講座では、関西大学教授の平井章一氏(以下、平井先生)を迎え、「『具体』再考 1-② 『具体』と万博-その光と影ー」をテーマに探求が行われた。かつて世界を熱狂させた大阪万博と、戦後日本を代表する芸術グループ 具体美術協会(以下、「具体」)。二つが交差した時の光と影とは何だったのか。本レポートでは、この刺激的な講座の体験を追ってみたい。
【ARTS STUDY 2025】 講座レポートVol.1/「具体」再考1-① 特殊講義1 はこちら
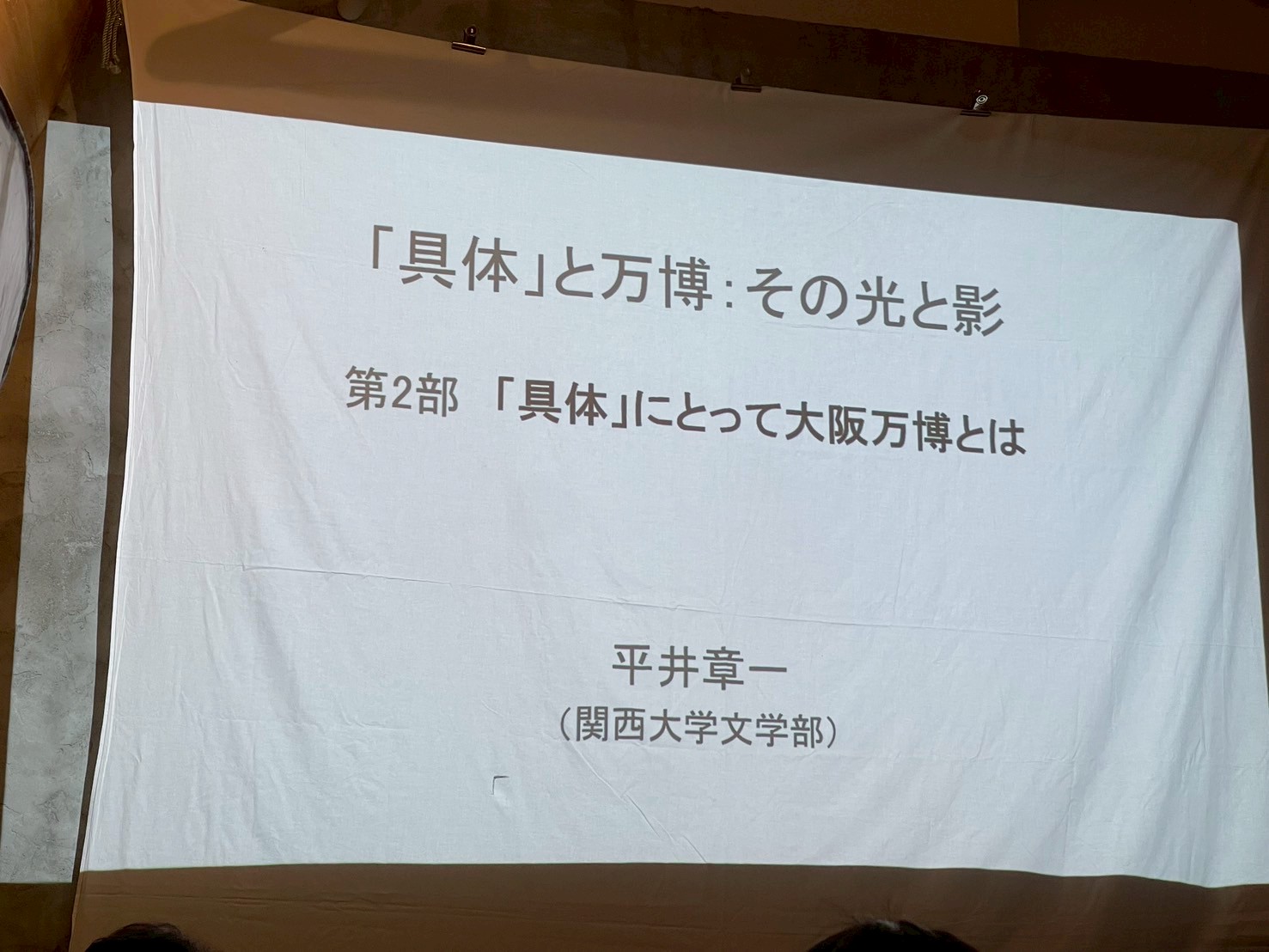
万博前夜、美術界の地殻変動
1970年の大阪万博へ向かう60年代後半、日本の美術界は大きな変革期にあった。60年代前半に流行した、感情を爆発させるような「熱い抽象(アンフォルメル)」は下火になり、代わって定規で引いたようなシャープで知的な「冷たい抽象(幾何学的抽象)」が新たな潮流となる。この変化は、高度経済成長という時代背景と深く結びついていた。
大量生産・大量消費社会の到来は、美術界にも影響を与える。アーティストたちはプラスチックやステンレスといった工業素材を多用し、モーターや電子音を組み込んだ新素材やテクノロジーを導入した「インターメディア」によるアートを生み出した。人間味を排したクールな表現が、時代の最先端とされ、無機的表現や機械的反復、図面を描いて発注して作品をつくる「発注芸術」も生まれた。さらに、アーティストの意識は絵画や彫刻の枠を超え、「空間」や「環境」へと拡張。空間全体を作品とする環境芸術や、野外彫刻展が盛んに行われた。美術が美術館を飛び出し、都市や自然へと展開していったのが、万博前夜の風景だった。
高度成長の光と影、そして反万博のうねり
未来への希望に満ちた高度経済成長だったが、その裏ではベトナム反戦運動や学生運動、公害問題といった社会の矛盾が噴出していた。「人類の進歩と調和」を掲げた大阪万博は、国家主導の巨大プロジェクトであり、未来の象徴だった。しかし、すべてのアーティストがこれを歓迎したわけではない。芸術が国家プロジェクトに利用されることへ、強い反発が生まれたのだ。
名古屋の「ゼロ次元」らによる「万博破壊共闘派」や、東京の美大生による「美共闘」は、過激なパフォーマンスで万博への反対を表明した。国家に協力する者と、それを拒絶する者。万博をめぐり、美術界は大きく分断されていた。

講座 「具体」再考1-② の様子
変容する「具体」―万博へと向かう道
この激動期、「具体」はどこに立っていたのか。1954年の結成以来、その姿を大きく変えていった。リーダー・吉原治良の「人の真似をするな」という檄のもと、初期は紙を突き破るパフォーマンスなど、常識を打ち破る斬新な活動で世界に衝撃を与えた。1957年以降の中期は、フランスの評論家ミシェル・タピエとの出会いを機に国際的な評価を得るが、活動は海外で紹介しやすい「絵画」が中心となる。
そして60年代後半、美術界の地殻変動を察知した吉原は「このままでは時代遅れになる」と大きな方向転換を決意。アクション中心の表現から、時代の潮流であった幾何学的でクールな抽象やテクノロジーアートへと舵を切る。これが後期「具体」であり、その先に大阪万博への参加があった。
万博という名の十字路―「具体」の葛藤と分裂
「具体」は万博で大規模な展示とパフォーマンス「具体美術まつり」を上演し、キャリアの集大成となる晴れ舞台を飾った。しかし、その内部では深刻な葛藤と亀裂が生じていた。テクノロジーアートで注目されたヨシダミノルは、反万博を掲げる「ゼロ次元」にも参加していたという。彼は万博直前に渡米しており、作品は本人が不在のまま展示された。その魂は別の場所にあったのかもしれない。
また、今井祝雄は、万博での体験を「鑑賞行為を与えられる印象」と語り、主体的な鑑賞が失われることへの違和感を覚えていた。彼が会場で発表したコンクリートの塊のような作品は、その静かな抵抗の表れだったのかもしれない。そして祭りの後、「具体美術まつり」の会計をめぐる金銭問題から人間関係が悪化し、中心メンバーが次々と脱退。大阪万博は、「具体」にとって最後の晴れ舞台であると同時に、崩壊へとつながる「導火線」となってしまった。
「具体」とは何だったのか?―問い直される前衛神話
最後に平井先生は、「具体は果たして『前衛美術グループ』だったのだろうか?」と根源的な問いを投げかけた。
「前衛」には体制に反抗するニュアンスがあるが、「具体」は異質だった。吉原が作品を審査し、彼の社会的信用から展覧会には財界人や行政の後援もついた。これは反体制を掲げる他のグループとは一線を画す。また、「精神の自由」というスローガンも、絶対的リーダーである吉原の美意識のもとでの自由であり、ある種の縛りが存在した。
このことから、「具体」を「前衛」と単純に括るのではなく、「抽象芸術団体」と捉える方が実態に近いといえる。しかし、それは「具体」の価値を貶めるものではない、と平井先生は語る。戦前と戦後を繋ぎ、日本のアーティストが初めて欧米の美術家と対等に協働し、日本美術をグローバルな文脈に乗せた功績は計り知れないからだ。
絶対的なリーダーとメンバーによる「合作」ともいえる「具体」のあり方は、個性を至上とする近代(モダニズム)を乗り越える可能性さえ秘めていたのかもしれない。講義は、そんな新たな視点を与えてくれた。
歴史の再発見、アートと対話する喜び
今回の講座は、大阪万博を軸に「具体」の多面的な姿を浮き彫りにする、スリリングな知的探求の旅だった。光と影、成功と軋轢といった普遍的なテーマを、美術を通して考える貴重な時間となり、「『具体』は前衛だったのか?」という問いは、私たちがアートに何を求めるのかという問いとなって返ってきた。
さらに万博という国を挙げての祭りとその時代および社会的背景が人や芸術に与えた変化も、現在行われている万博とあわせて考えさせられた。万博が生み出すもの、そして残すものは何なのか?今に照らして考えてみたい。歴史を知ることは未来を考えること。その面白さと奥深さを改めて実感させられた。

会場「BARまどゐ」外観
「『具体』再考」の次回講座(3回目)は12月28日㈰にAAP(アシヤ・アート・プロジェクト)副実行委員長でダンサーの岡登志子と平井先生の特殊講義 「やってみるからはじめよう―「具体」の創造精神に触れる:レクチャー&パフォーマンス+ワークショップ」を開催。現在受講生募集中。【ARTS STUDY 2025】のディレクターはC.A.P.メンバーの山下和也。
【ARTS STUDY 2025】では、今後も様々なテーマで知的好奇心を刺激する講座が続きます。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
